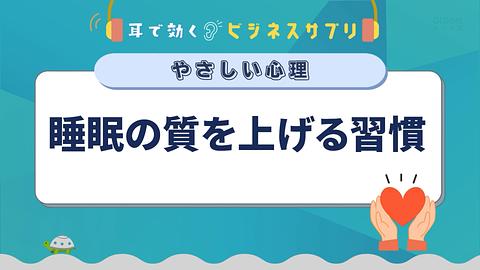社内政治の傾向と対策を考える本連載も最終回。社内ポジションが勝る上司に勝ちにいくパターン4「上司に戦いを挑む」を考える。ケースの主人公はグロービス経営大学院生の山口さん(仮名)だ。
パターン4: 上司に戦いを挑む(3)
 【ケース】
【ケース】
IT機器開発企業D社に勤める山口は、苦しい立場に置かれてしまった。事業部の売上が伸びないことを理由に直属上司の正田が解任され、黒松が事業部全体を仕切る上司となったのだ。数カ月前、黒松から引き抜きのオファーを受けたが、山口はそれを断っていた。
黒松は山口のことを良く思っていなかった。顧客から信頼されている山口に対する嫉妬心すら抱いていた。そして、山口への攻撃が始まった。事業部の成績が伸び悩んでいるのは、山口のチームワークを無視したスタンドプレーにあるというのだ。日々の経費申請を承認しないといったことを含めて嫌がらせはエスカレートし、山口は使えるリソースをほとんど失った。山口は何よりも顧客のために身を粉にして働き、日本を代表するE社などから高い信頼を勝ちえてきただけに歯がゆかった。
そんな中、D社の業績は急激に悪化していた。日本法人トップ村中も事業部長の黒松も、有効な打開策を打ち出せていなかったからだ。こうした経営メンバーの力量不足と自社の行く末を誰よりも憂いていたのは山口だった。その心境をプロジェクトで交流のあった米国本社の仲間にメールした。「この状況を米国本社が看過するはずがない。もう少しの辛抱だ」と。
その1通のメールが米国上層部に伝わったのか否かは不明だが、ついにそのときが来た。業績不振を見かねた米国本社から、やり手のディレクターが派遣され、実態把握のための現場インタビューが始まった。日本から米国本社には情報が正しく伝わっていないことが次々に明らかになった。例えば、山口は実績を上げているのにもかかわらず、最低ランクの評価がリポートされていたのだ。
米国本社のディレクターは山口に対して「日本法人の改革に協力してくれないか」と持ちかけられた。
山口にとっては、一筋の光明が見えた瞬間だった。「これで顧客第一の健全な組織に変われる。やはり正義は勝つんだ」。山口は、日本法人の経営陣が機能していないなど現状を細かく電子メールでレポートした。
しかし、想定外のことが起こった。なんと、このメールを黒松派にハッキングされたのだ。黒松は米国サイドに先に手を回し、山口の内部告発を封殺した。このあたりのしたたかさは黒松の方が数段上だった。山口はリカバリーしようと米国側に接触を試みたが、言葉のハンディもありこの難しい局面を乗り越えることはできなかった。
結局、日本法人の改革は進められることにはなったものの、山口は居場所を失い、退職を余儀なくされた。
「公正世界仮説」にはまっていないか?
【講師解説】
動かしたい社内の究極の上司は経営トップである。トップが恐れるステークホルダーである重要顧客、株主、親会社、トップが信頼する外部の助言者(社外取締役など)、指名委員会などが動き出すタイミングを見逃してはならない。
今回のケースでは、S社米国本社から目をつけられることが日本法人の経営陣にとって一番怖いことだったはずだ。山口はその米国本社とのパイプ(リレーショナル・パワー)を活かそうとした。しかし、最後の段階でメールがハッキングされ失脚してしまった。
正義感の研究で先駆的業績を上げたメルビン・ラーナーは、「世の中は公正にできていると考えたがる世界観 = 公正世界仮説(just-world hypothesis)」を打ち出した。ラーナーによると、人間は世界は予測可能・理解可能であり、自分の力でコントロールできると考えたがるという習性を持つ。それが高じると、良い人は報われ、悪い人は罰せされるようにできていると考えたがる(注1)
D社の米国本社から送り込まれたディレクターが日本法人の改革に乗り出した時、山口にとって「正義は勝つ」ということの証左に映ったことだろう。
したたかに行動することは勝つための必要条件だ。しかし、それを満たしても必ず正義が勝つとは限らない。この現実に真正面から向き合おう。

だが、だからといって諦めるのか?
いや、諦めてはならない。正義のために戦った姿勢は組織のメンバーに記憶され、その魂は生き続ける。諦めることは自らの「矜持」と「志」を放棄することになる。
■最後に
1度しかない人生、自分のエネルギーの源泉になる価値観に火をつけ、爆発させたい。その貴重なエネルギーを無駄に組織の内側の戦いにばかり費やしてしまうのはあまりにもったいない。今回の連載が、何かの気づきにつながれば幸いだ。(連載完)
(注1)Melvin J. Lerner, The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion (New York: Plenum, 1980).







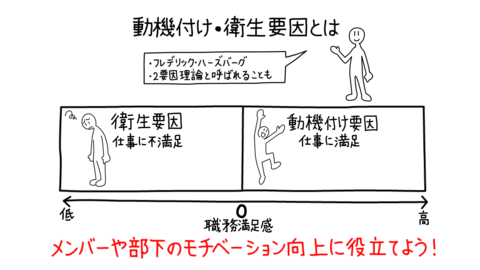



















%20(5).png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)