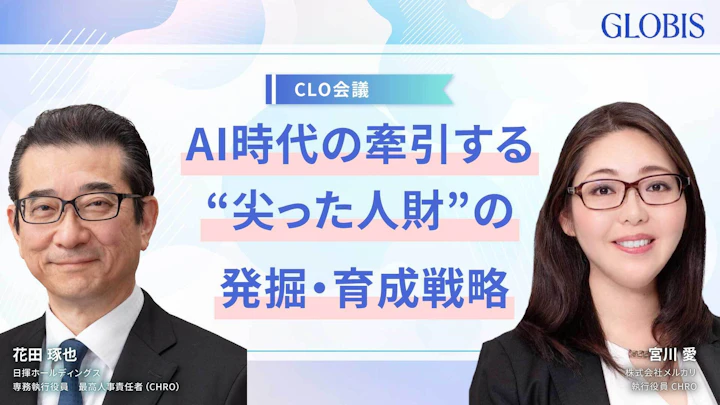「面積と比して非常にバラエティに富んだ気候風土が食材の多様性をもたらした」(辻)
 辻芳樹氏
辻芳樹氏
楠本修二郎氏(以下、敬称略):日本、とりわけ京都には数百年続いている会社も多い。私も京都では「伊右衛門サロン京都」を徳岡さんともご一緒にやらせていただいている。で、そこでよく言われるのは、伝統ある会社は単にその時代を生き延びてきた訳でなく時代に合わせて革新を繰り返してきたということだ。月桂冠さんはその最たる例だろう。「変化に対応するものが生き延びる」というダーウィンの言葉通り、革新を繰り返しながら数百年生き延びてきたその結果として伝統があるのだと思う。
今日はまず「日本の食文化とはどういったものか」という共通理解を深めていこう。辻さんは2010年、徳岡さんを含む39人の日本人シェフとともに、アメリカのナパバレーにあるCIA(The Culinary Institute of America)という料理大学で日本の食文化に関する講演をなさった。今日はそのサマリーもご用意いただいたそうなので、まずはその辺からご説明いただけないだろうか。
辻芳樹氏(以下、敬称略):日本の食文化の歴史を簡単に、1000年を10分に凝縮してお話ししたい。今日はCIAや韓国で講演したときの資料をダイジェストにしてみたが、これは日本料理の特質性を「伝統と革新、そしてそこから生まれた多様性」という切り口で紹介したものだ。日本は外から入ってきたものに独自の工夫を施し、それを進化させたうえで革新的なものを生み出してきた。そしてそれを日本的伝統に仕上げていった訳だ。食文化でもそうした伝統と革新のサイクルが文化的エンジンとなり、結果として多様性という豊かさを持つに至ったというのが私の基本的な考えになる。
その概要をお話しすると、まずは日本列島の地理的特異性。これは日本の食文化を考えるうえで欠かせない要素だ。周囲100m以上の島をカウントすると、日本にはなんと大小6852もの島がある。また、この島の数と入り組んだ海岸のおかげで日本の海岸線は3万3889kmもの距離におよんでいる。これはアメリカの約1.5倍だ。さらに北の亜寒帯から温帯、南の亜寒帯まで距離にして3000kmの日本列島は、面積は小さくても気候的条件という点で大変バラエティに富んだ環境にあると言える。
また、狭い国土の特徴として山と海が近接しており、川が毛細血管のように国土を流れている。そのなかで山の豊かな栄養が海に注がれ、世界的にも優秀な漁場が近海でつくりあげられてきた。そうした環境下、多種多様な漁業、海藻類などの採取・栽培、その加工技術等が発達してきた訳だ。暖流と寒流が列島の東西でそれぞれ出会うことによって多様な魚の育成を促し、魚の身も大変上質なものになっている。統計によると日本の主要魚種の15%以上は日本近くの海洋で見つけることが出来る。
全漁獲量の8割が何魚種に占められているかを海外と比較すれば、その多様性もよく理解出来る。たとえばノルウェーやアイスランドといった北欧の漁業大国ではサケやマス、ニシンなど5〜6種類なのに対し、日本はイワシ、サンマ、イカ、ホタテ、マグロ、カツオなど18種類だ。
一方、歴史的側面についてもお話ししたい。多くの研究者が指摘している通り、日本の食が持つ体系の特徴として、古代国家の時代からはじまっていた国策としての稲作および水田奨励が挙げられる。そこに列島の自然条件が相まって、米、魚、そして野菜という食事システムの基盤が出来あがっていった。ここに肉が含まれないのは大陸から渡来した仏教思想の影響も大いにある。
また、日本の食文化の歴史は、大陸つまり中国をはじめとした様々な地域からの影響を日本的に変容・変化させてきた歴史とも言える。縄文後期にはじまる稲作を含め、食と農業に関わるほとんどの分野は外部からもたらされたものだ。そこに日本の風土と文化に合わせてまったく新しい価値を創造する。それが日本の食文化が持つ本質的スタイルであり、アイデンティティと言える。
そのポイントは圧倒的な中国文化の影響と、16世紀の大航海時代を生きていた西洋文化との出会いだ。西欧文化とは江戸時代を挟んだ明治維新以降、再び衝撃的な出会いを果たしている。ただ、二つの大文明に出会って色々なジャンルの文物を吸収しながらも、日本は最終的に自分たちのアイデンティティを失うことなく今日まで来たと考えている。特に民族のアイデンティティにおける2大要素でもある言語と食文化。この点に関しては揺るぎない日本固有のものを我々は保持し続けている。
「茶の湯に匹敵する料理の美学と精進料理の系譜を継ぐ先端技術が生んだ『懐石』という極み」(辻)
辻:日本の食文化を考えるうえで重要な大都市の文化にも触れておきたい。つまり、江戸、京都、大阪だ。外部からの文化を受け入れてきた日本が例外的に国を閉じた江戸時代、内戦もない徳川政権下で全国に物流網が整備されたことは独自の食文化発達に大きく貢献した。そして、天皇の都である京都、商人の町である大阪、将軍と町民がつくりあげた大都会江戸。この3都市がそれぞれの個性を生かして食文化を築きあげた江戸時代、日本の食文化の骨格が完成したと言える。
江戸時代に生まれて流行した歌舞伎、相撲、着物等は今も和風文化の定番となっているが、料理文化をとってみても、たとえばさまざまな料理本の出版ブームがこの時代にあった。料理のガイドブックやレシピ本、あるいは評判記まで登場しており、当時は江戸で評判の料理屋を相撲の番付票に見立てて紹介したものまであった。
江戸時代、新興の大都会江戸はずば抜けて巨大になり、そこには一旗掲げようとする武士や町人、そして商人や職人が全国から集まってきた。しかも集まってきた人々のほとんどは男だ。単身赴任者が増えた江戸では自ずと飲食店が大繁盛した。そこで生まれた江戸のファーストフードとも言える寿司、天ぷら、鰻、蕎麦等は、今でも世界で通用する日本料理の代表選手だ。明治以降の日本では西洋料理に影響を受けた新しい料理が次々と生まれていくが、そうした近代化の荒波に対応出来るだけのポテンシャルは、実は江戸時代に用意されていたと言える。
最後に海外でも必ず話題となる懐石に触れたい。料理における懐石とは何か。外国の方々から何十回とこの質問を受けてもまったく答えることが出来ない時期があった。これは非常に難しい問いだ。ただ、多くの研究者が指摘している通り、懐石料理の誕生については二つの大きなファクターが存在する。
まずは中国仏教の禅宗からもたらされた精進料理。精進料理は日本の料理技術発展に大変貢献した料理体系だ。精進料理は、中国の宮廷料理から影響を受けて出来上がった大饗料理、そしてそこから生まれた武家の本膳料理における形式主義を打ち破り、調理における技術革新をもたらした。第二のファクターは茶の文化だ。これも中国からもたらされた、その後は日本独自の進化・発展を遂げてきた。そして茶の湯の文化が、お茶を楽しむための食事として懐石料理を生み出した訳だ。
精進料理は鎌倉時代、中国に留学した禅僧たちが持ち帰った料理だ。しかし肉食厳禁という宗教的戒律から生まれたこの料理は、制約のなかで逆説的に工夫を重ねるうち、ある種の美味しさ、そして“らしさ”を追求する料理になっていった。その結果として料理技術が発達し、洗練されていった訳だ。
一方、お茶の文化はとてつもない飲食文化を構築した。栽培・製法においても日本独自の洗練と進化を重ねた茶の湯の文化は、日本的な建築、お花、美術品、工芸品などを含めた総合芸術となっていく。そして公家や有力な武家、さらには裕福な豪商たちがパトロンとなり、日本独自のサロン文化へと発展した。その洗練された美学に拮抗する料理の美学と、精進料理の系譜を継ぐ料理の先端テクノロジーが出会い、そこで築き上げられたのが懐石料理と言えるのではないか。
以上の話をまとめると、15〜16世紀の室町時代にある程度完成した日本料理が、最終的に日本固有の食文化と呼べる段階になったのは江戸時代であったいうことになる。明治維新以降は開国とともに肉食の解禁をはじめ、西洋料理の影響が日本料理に新たな局面をもたらしていく。ただ、そこでも西洋料理に日本料理自体が吸収されるのでなく、逆に日本流が持つ料理体系のなかに飲み込む形で独自の西洋料理を実現していった。つまり洋食というジャンルだ。
日本の食文化はそんな風にして海外の圧倒的な影響にさらされ、それを受容するようなふりをしながらも、結局は日本独自のものを残し、守るというスタイルを貫いてきた。私としては、それが現代もまだ続いているように見える。外部からやってきた文化の受容とその変容および進化、そして洗練というプロセスにかけてピカ一の力を持っているのが日本の食文化ということではないかと思う。課題があるとすれば、そうした文化を今度はどうやって海外に発信していくべきか、だ。伝達して教育すべきなのか。この辺は苦手なのかもしれないし、今後の課題だとも思う。(会場拍手)。
楠本:海流、四季折々の気候、海岸線の豊富さ、あるいは川が果たす役割といった地理的特徴のほか、中国や西洋の文化を受け入れるなかで独特の発展をしてきたという歴史的経緯もお話しいただいた。そうした革新の繰り返しこそ、伝統が育まれた理由だと思う。そのなかで、たとえばアジアでは今、日本のハンバーグやとんかつが「日式洋食」として親しまれている。ジャパニーズスタイルの洋食を日本の食文化として海外に発信出来るところまで、今は至りつつある訳だ。ただ、辻さんのお話通り、海外への発信という点ではまだまだ弱いと思う。
続いて徳岡さんに伺っていこう。辻さんからは懐石のお話もあったが、海外の方々が憧れを抱くそうした料理の本質を、海外へ伝えていくのは相当大変な作業であるとも感じる。その辺も含め、伝統を守りながら海外にチャレンジしていらっしゃる徳岡さんのご意見を伺っていこう。また、徳岡さんは常に「一次産業が日本の食を支えてきたのだ」ということも熱く語ってもいらっしゃる。日本の食を支えてきた一次産業の視点も踏まえつつ、伝統と革新についてコメントをいただきたい。
「一次産品を生産技術や人ごと海外に発信し、国内の地域活性化にも結び付ける」(徳岡)
 徳岡邦夫氏
徳岡邦夫氏
徳岡邦夫氏(以下、敬称略):懐石のような料理が伝わりにくいという点について言えば、風土や生活スタイル、そしてそのなかで培われてきた価値観も違ってくるので当然ではあると思う。ただ、価値観の違いはあれども同じ人間である以上、本質的には同じという思いもある。今、たとえば健康や美容といった切り口できちんと伝えることは出来ていないが、そうした共通の切り口で伝えるのは可能だと思う。
あと、理解して貰うにはやはり体験して貰うのが一番だとも思う。私たちも料理店を営んでいるが、日本で出している料理をそのまま海外へ持っていっていくのは…、出来ないことはないが、かなり難しい。水から何からすべて違う環境で育った食材を使うのであれば、日本の味を再現するためにかなりのコストが発生するだろう。食べる場所も環境も違う訳で、相当難しい。その意味では日本に来ていただいて、日本の自然に囲まれた環境で体感して貰うのが最も良いのかなと思う。
農業など一次産業にも言及しておくと、日本でも海外でも、とにかく料理の世界で注目されるのは料理人だ。最近では一次産業に従事する方々も徐々に注目を集めてきたが、まだまだ注目が足りない。私自身は料理を改善・進化させるため、もしくは時代に適用させるため、色々と悩みながら突き詰めていった結果として必然的に食材へ行き着いた。そこで流通を経由せず直接生産者のもとへ出掛けていったのだが、そこで一次産業に従事する方々の生活や仕事、考え方やネットワークに触れて、なんというか…、すごくひずんだものを感じた。「世ためになることをしているのに報われない」という環境で、メンタル的にも少しねじれているというか、ずれている部分がある。それで経済的にも恵まれていないという印象を強く受けた。
食に携わる身としてそうしたねじれを正すというか、健全にすべきではないかと思っている。それで、地域の活性化に加えて「世界への発信が出来たら」と考えた。たとえば海外のイベントでは目先の技術等だけでなく、日本の一次産業が果たす役割といったものを必ず伝えている。そのうえで、「日本で積み上げられた一次産業のノウハウは世界が幸せになるために必要なものなんだ」と。人類にとって重要なのではないかといった提案をしている。今後、徐々にそうした視点を実際の商品やサービスにしたうえで仕掛けていこうと考えている。
で、その際は農産物だけでなく水産品も持っていきたい。そして独特の気候で培われたノウハウや流通システム、あるいは消費者の価値観も併せて、健康や美容への効果、そして長寿ということも謳いながら伝えていきたい。魚だけでなく、たとえば鶏も、だ。ヘルシーでかつジューシーな日本の鶏は本当に美味しい。食べる部位も料理法も違うので、その辺でも表現出来るのではないかと思う。
我々としては一次産品をそのまま、もしくは加工して持っていくのではなく、「向こうでつくってしまおう」と。そこに日本人の勤勉さや真面目さが生み出した正確な流通網を構築していけば、新しい価値観も根付くと思う。それによって進出した地域の方々も幸せになると思うし、実際に今はそれをやろうとしている。
楠本:「世界が幸せになるために必要だ」というのは本質的で大変分かりやすく、かつ強烈なメッセージだ。商売の原点でもあると思う。CIAで今年議論されるテーマは「食のグローバリゼーション」だったと思う。グローバリゼーションとは、平たく言えば世界がひとつになっていくプロセスのなかで均一化していくこと。食は最もドメスティックな分野だが、そこにもグローバリゼーションの波が来たと考えているのだろう。
そこに徳岡さんをはじめとした日本料理の関係者が参加をする訳だ。これは、「食のグローバリゼーションにおいて日本食の果たす役割が非常に大きい」と、アメリカ人が理解しているということだと思う。逆に言えば日本がそこでどのように食の文化を発信し、ビジネスに繋げていくのかを問われているのだと思う。
「日本酒づくりの歴史は革新の繰り返し。それがたまたま結果として『伝統』となった」(大倉)
 大倉治彦氏
大倉治彦氏
楠本:では続いて大倉さん。日本酒はすでに世界へ打って出て、成功も収めている。その意味では日本食のグローバリゼーションにおける急先鋒のひとつだと思う。そうした海外でのご活躍に関して、日本酒の歴史も踏まえながらご説明いただきたい。
大倉治彦氏(以下、敬称略):月桂冠は1637年、寛永14年に創業した。江戸時代初期、徳川三代将軍のときだ。私は月桂冠大倉家の14代目になるが、当社は今年で376年目になる。で、今日のテーマである伝統と革新という視点も絡めてお話しすると、日本酒づくりの歴史はまさに革新の繰り返しだった。それがたまたま積み重なって伝統になっているのだと思う。現在の月桂冠は日本酒でトップ3に入るほどの大メーカーだが、実は江戸時代の250年間は伏見の小さな地酒屋に過ぎなかった。
それが急成長するようになったのは明治の後半、私の曽祖父が西洋の技術を他のメーカーに先駆けて採り入れ、近代的なノウハウでお酒造りをはじめたことに端を発している。明治42年に大倉酒造研究所という部門をつくり、東大卒の技師を雇って研究をはじめた。それまでは杜氏さんの勘と職人技だけでつくっていたが、そこに近代技術を導入していったと。それが最も早かったために急成長したという歴史だ。
それと国際化についてもお話をすると、我々は現在、カリフォルニアにも工場を持っている。つくったのは20年前だ。他の国にも販売拠点はあるが、工場は日米のみ。そこで、当然ながら現地カリフォルニア産のお米と水で日本酒をつくっている。
今は世界的にそうだが、特にアメリカは日本食ブームの只中にある。きっかけのひとつは、「ダイエットには肉よりも魚のほうが良い」という話だった。当時は主にバブルが弾けて日本人駐在員などが皆日本へ引き上げていった時期だ。日本食を食べる人も少なくなり、現地の日本食レストランも一旦は寂れていった。そのあと新たな日本食レストランが雨後の筍のようにあちこちで出来はじめたが、そうしたレストランのほとんどは昔と違って中国人か韓国人が経営する店だった。日本人の調理人がまったくいない店も多く、食べに来るのも現地の方々ばかりだった。つくる側にも食べる側にも日本人関与していないところで日本食が大変な勢いで広まっていった訳だ。
で、そういったお店に行くととんでもない料理に出会うことも多い。たとえばアボカドとカニカマをご飯に巻いてスパイシーなソースで食べる、いわゆるカリフォルニアロール。あるいはキャタピラロールはご存知だろうか。ご飯の上にアボカドを並べたもので、キャタピラは青虫のこと。つまり青虫ロールだ。そういうものをお醤油につけて食べている。日本の接待でキャタピラロールを出したらどつかれると思うが(会場笑)。
そこで月桂冠の社長として申しあげると、日本酒の味をアメリカ人が本当に分かっているかどうか、まったく分からない(会場笑)。日本食を食べるときに日本食を飲んでくれているのは間違いない。ただ、「日本食を食べるときは日本酒を」という組み合わせ感覚で飲んでいるのか、それとも日本酒自体の味を本当に美味しいと認識して飲んでくれているのか…。売上が大変伸びているのは事実だが。
従って主に中国人や韓国人の方々が経営しているそうした日本食レストランは、日本人の利益にあまり貢献していない。ただ、そこに日本酒やお醤油を供給する我々としては商売になるので、その意味ではこれからもどんどん増えて欲しいと思う。
楠本:アメリカの方々も、「やっぱり日本食には日本酒が合うね」と思って飲んでいらっしゃるのではないだろうか。
大倉:「合うな」と思っているとは思う。ただ、それを自分で判断しているのか、「合う」という固定概念をそのまま受け入れているのかどうかが分からない。日本人は海外の日本食レストランでもビールも飲むが、そこでは海外の方のほうが日本酒に対するロイヤリティが高い。飛行機でも同じだ。ビジネスクラスで和食か洋食かを聞かれたとき、私は洋食を選んでビールを飲んだりしている。で、隣の白人男性は和食と日本酒を選んでいたりして、もう完全に逆転しているという(会場笑)。
楠本:たしかアメリカの人々が日本食を食べはじめたときは二つの点に注目していたと思う。ひとつは日本が長寿の国であるという点だ。「つまり健康食ということだね」と。それともうひとつ、日本人女性の肌が美しいというポイントもあった。美容にも良いという訳だ。そうした理屈で入ってくる面があったと聞いている。アメリカで講演する機会が多く、当地での評価も大変高い徳岡さんはどうだろう。彼らと話をしていて、何か日本食を発信する際のポイントとしてお考えになっているものがあれば。
「日本食が背負って立つ精神性や神秘性が欧米から逆転的に羨望されている側面もある」(楠本)
徳岡:今は日本食を食べる際に日本酒を飲むというのがトレンドになっているのだと思う。ただ、そのファクターは健康や美容よりも、むしろ見た目ではないか。ぱっと見て、違うと分かる。イタリアンとフレンチのお皿が出されて「どっちがどっち?」と聞かれたら、恐らく特徴的な食材を使っていない限りは見分けもつきにくいと思う。しかしそこで…、日本料理はぱっと見て「あ、違う」というものがある。さらに言えば、料理のなかに禅宗や茶道といった精神的な要素が含まれていて、オリエンタリズムというか、神秘的な感覚があるのだと思う。分からない要素が多いと。
楠本:たしかに彼らは‘sense of wonder’という言葉をよく使う。
徳岡:もしかしたら、今流行っている日本のアニメにもそうした感覚的あるいは精神的な要素を感じているのかもしれない。日本食の技術は素晴らしいが、いずれにせよトレンドになっている理由は「技術や色彩が凄いから」というより、むしろ料理のなかに日本のストーリーやスピリッツといったものを見出しているからだと感じる。それが彼らにとってワンダーランドなのだろう。「こんなことはあり得ないけれど、実際に起きるといいね」といった要素があり、震災ではそれが実際に日本では起きた訳だ。彼らとしては「え?」という感覚だと思う。「日本ってすごいんじゃないの?」と。
楠本:あれほどの震災でも暴動が起きなかった、あるいは助け合いが起きたという部分を彼らは見ていたという。
徳岡:アニメのなかで見ていたようなことが現実に起きたと。そういう精神的なものに見た目が関係しているのだと思う。それに対する憧れのような感覚があって、それを知っていることで帰属の欲求を満たすことが出来る訳だ。そこにいることで自分がハイクオリティな人であると認識出来る。いわゆるブランドを形成したのだと思う。それは日本人が意図していた出し方ではなかったが、世界中の人はそのように判断したうえでとりあげた。で、「それならビジネスにしようか」と言って中国人の方々が日本食レストランをつくるというような、そんな構図になっていると感じる。
楠本:ということは、日本が繰り返してきた伝統と革新という方向に、どちらかというと世界が近づいてきているという…。
徳岡:それを知っていること、あるいは嗜んでいることによって、自分の文化度が上がるというか、ステータスを得ることが出来る。人にもそれを表現しやすい。まさにブランドだ。
楠本:最初は健康や美容といった機能として入っていったけれども、それが徐々にブランド化していったと。
徳岡:感応というか、自己と同一化することによるステータスというか、自分を表現する材料になっているのではないか感じる。だからこそその次に何をするかが大事になる。
楠本:そうなると文化的な憧れという意味で日米逆転構造もあり得ると思う。
徳岡:そう思う。戦後の日本では欧米の文化に憧れて新しい生活スタイルが出来上がっていった。しかしそのなかでも日本的なものは残っていたというか、それが日本人にとっても大事なものになっていたのだと思う。で、それが今は海外の人にとって憧れになっているという訳だ。たとえば京都の祇園にはそういう面がある。
楠本:日本食が世界から憧れを集めているという観点について、辻さんはどうお考えだろう。たとえば今はミシュランの星が付いたレストランでの厨房であれば、ほぼ2番手か3番手に、少なくとも4番手ぐらいに日本人料理人の方がいらしたりする。その辺を含めて日本食のステータスが上がり、ブランド化してきていると感じるが。
「こと海外では文化はまず知的層によって本質的な理解がされ、そして発信される」(辻)
辻:日本食のブランドは数十年前から確立していると思う。ただ、それが確立してきた数十年にわたる過程のなかで、国策としてきちんとした方策が出されず、ただただ流失が進んでいた。日本人が日本料理を出していくとき、何を輸出したいのか、何を商売にしたいのか、どんなレベルで商売をしたいのか、等々。結局のところ最後は商売の話になるが、そうした政策が明確にされないまま月日が経ってしまい、現在の結果に至っている。文化としては海外でもたしかに確立されていると思うが。
それと文化の発信という視点についてもうひとつ。文化というものは…、日本では大衆娯楽が文化や伝統に変わっていく流れもあると思うが、こと海外ではどちらかと言えば知的層から入ってくるものだ。まず知的層が異文化に興味を持って、本質的にその価値を理解していく。そこで書籍等にしたりする訳だ。
日本酒についても同じ。パリやロンドンやニューヨークでは酒バーに知的層が集まり、「谷崎の文学はね」なんていう話を飲みながらしている。蕎麦の文化も同様だ。パリにも古くから蕎麦屋があり、そこでフランスの知的層が日本文学をフランス語で読みながら蕎麦をすすっていたりする。そういうシーンは20年以上前からあった。
それと、先ほど徳岡さんが「同じ人間であり、本質的な価値観は通じる」といったお話をなさっていたが、こと味覚に関して言うと共有が非常に難しい。従って啓蒙しなければいけないと思う。過去30年間、なんの政策もなしに日本ブランドがたれ流されてきたと言ったが、味覚の価値観が違うというのが一番の大きな問題だ。そこで重要なのは通信手段。味覚の価値観をどうやって通信させていくかになる。
方法は三つあると思う。まずは大倉さんが触れていたような世界だ。体系化された日本料理の文化を滅茶苦茶に崩して、一切のルールをなくし、たとえばカリフォルニアロールにしたりする。日本人のなかでさえ価値観の相違はあるが、全体として「これは恥ずかしいんじゃないの?」と思うほど、滅茶苦茶に崩す。この場合、たとえばどこの国の方がオーナーであってもいいと思う。それはまた別の問題だから。とにかく崩すというのはひとつの発信方法だし、間違っているとは思わない。世界中の日本料理が滅茶苦茶という状況である以上、それもグローバル化と言えるだろう。
で、二つ目は日本料理が本質的に持つ技術的バックボーンの活用だ。それが過去20年間、世界の料理にどれほどの影響を与えたか。この辺は徳岡さんが徹底的に研究なさっている領域だが、日本料理にはならずとも日本料理の技術は世界中の料理をお皿の下で支えている。そうした技術の本質論は、料理人同士の交流が生まれてから初めて問われるようになった。昔は少しわさびを添えてみる、あるいは何かの料理に大量の醤油をかけて‘Oh, Japanese.’と言っている程度だった。しかし今は出汁の力がいかに料理を支えているかといったことを料理人が分かるようになってきた。そのうえで新しい料理が模索され、それを知的層が口にしていると。そこでも文化の発信は成り立っていくと思う。
そして三つ目の方法は日本の枠を確実に守って発信すること。ただ、ここでもある程度の妥協は絶対に必要だ。海外の人々はお吸い物を好まない。もちろん徳岡さんのお店に来るような方は本当においしいお椀を体験し、その新しい味覚に感動することもあるが、大抵の人は分からない。風土と生活観がまったく違うから。ただ、いずれにせよ今は、たとえば懐石という形で日本料理が確実に枠をつくっている。多少の妥協はあるにせよ、そうした本物の日本料理をそのまま発信する力も日本人は持っているし、その味覚を受け入れることの出来る人々も世界にはいる。
楠本:一方では良いものを正しく、伝統を守りながらしっかりと出していく方法があって、しかしもう一方ではそれを崩す方法もあると。最新の統計か何かでは、現在、日本食レストランは世界に5万軒あるという。ただ、日本人が経営している店舗はそのうち10%だそうだ。その他4万5000軒は日本食のブランド力に頼んで、あるいはなんとなくブームということで、いささかまがい物ではあっても「ビジネスだからやっちゃえ」という方々という話だろう。で、恐らくこの流れは今後も加速すると感じる。
そう考えると、今は一方では攻めなければいけないが、ある意味で日本の食文化を守らなければならないタイミングでもあると思う。ある官僚の方は「COOL JAPAN戦略とは防衛であり、その予算は国防費でもある」という言い方をなさっていて、「あ、なるほどね」と思ったことがある。日本の食文化を守るというのは、言い換えると日本が古来より持つ価値をよその国のものであるかのように切り崩されないようにすることであると。ただ、一方では外に向けたビジネスチャンスもどんどん広がっている訳で、とにかく両面があるということだと思う。さて、そろそろQ&Aに移ろう。

「“日本食材の営業マン”となり、日本を元気にすることに貢献したい」(徳岡)
徳岡:はいっ!(と手をあげて)大倉さんに質問です(会場笑)。20年前から海外で日本酒をつくられているとのことだが、日本と同じクオリティには出来ないのではないか。色々と改善はなさっていると思うが、水とお米がまず違うし、土壌も空気も気候も違う。そのなかで同じものが出来ているのか、もしくはまだまだ改善の余地があるのか。あと、メーカーさんと農業との関係についても伺いたい。どのような指導をなさったうえで、たとえばカリフォルニア産の日本米を改善しているのかもお伺いしたい。
大倉:まず、技術的には日本とまったく同じ品質の日本酒が出来る。ワイン等と異なり、日本酒づくりでは原材料よりも技術のほうが製品に与える影響が大きい。酵母は日本から持っていくので同じだが、たしかに米と水は日本と違う。しかしそこは技術の力でいくらでも調節出来るし、日本と同じ品質のものが出来る。
で、現地農業との関係について言うと、日本と違って我々の生産規模がまだ小さいこともあり…、逆に言えば向こうは農業の規模が大きいこともあり、我々が指導するということはない。単に買う立場だ。ただし、山田錦や五百万石のような酒造好適米は向こうでは手に入らないから飯米でつくっている。従って吟醸等特別なお酒はつくることが出来ないため、アメリカでその注文があれば日本から持っていく状況だ。
徳岡:好適米が出来るのなら、やはり使いたいと感じるのではないかと思う。日本人を連れて行ってアメリカでそれをつくるのは可能だろうか。気候等違うと思うが。
大倉:たとえば山田錦は兵庫県の三田市辺りで生産されているが、そのノウハウは門外不出と言われている。で、それを他の県でこっそり栽培する人はいるようだが、やはり国内でも同じ味にはならない。その意味では山田錦をアメリカで生産しても…、栽培自体は出来ると思うが、同じ品質にはならないと思う。
会場:壇上には、料理人を育てる方、料理を提供する方、そのプラットフォームを提供する方、そして日本酒をつくる方が揃っている。皆さまで何か新しい革新を起こしてみたいといったアイディアや思いがもしあれば、ぜひお聞かせいただきたい(53:00)
徳岡:「お前ら口では大きいことを言っているが、実際に何か出来るのか?」と(会場笑)。
辻:大倉さんには1000年の企業を経営している方のサバイバル本能といったものを強く感じる。従って個人的アドバイザリーボードのような形で、感性のまま、「これは日本だ」、「これは日本じゃない!」といったコメントをいただけたらと思う。
で、徳岡さんとは、たとえばどこかの調理場で1カ月ほど缶詰めになって技術革新を進めたい。そこで生まれた新商品を徳岡さんのお店で出しても良いし、私がニューヨークでやっている日本料理のお店で出しても良いと思う。とにかく知識の宝庫であるし、これほどの伝統と美学を料理で体現しているにも関わらず、そのフレームワークを完全に崩して最初からつくりだす力も持っているという、日本でも数少ない料理人のひとりだ。その意味では研究機関のようなところで…、調理科学や分析といった話ではなく、「料理とは何か」を最初から見つめ直しつつ、ご一緒に勉強したい。
楠本:ビジネスになるかどうかは分からないが、ひとつのプラットフォームというかコミュニティとして、そういったラボが出来たら良いなと私も思う。
会場:少子高齢化が進む国内でどのようにして技術を継承していこうとお考えだろうか。個人的には外国の若い方々を国内に招いて育てるべきだと思うし、そこで日本の食文化と海外の価値観を織り交ぜながら革新を起こしていくしかないと思う。(55:50)
会場: ‘sense of wonder’というか、食に関する日本精神のコアを世界に発信していくのは本当に大変な作業だと感じるが、具体的にはどのように伝えていこうとお考えだろうか。私は製造業で働いているが、何か繋がるものがあればと感じた。
会場:日本食がどんどん海外へ出ている今、一方では国内の消費量が落ち込んでいる側面もあると思う。今日お話しいただいた点以外で日本食のグローバル化におけるメリットやデメリットが何かあればぜひお聞かせいただきたい。
徳岡:まとめてお話ししたい。私としては「日本を元気にしたい」という思いが根底にある。現在、企業は為替等々で株価も上がっているし、アベノミクスという政策も必要だとは思う。ただ、たとえば福島の方々等、「地方の人々が元気になるためにどうすれば良いのか」と。地方の人々は「実際のところ、普通の生活がしたい」とおっしゃる。自分たちで頑張って、世の中にそれが評価されて、そして報われるというプロセスのなかで経済的にもメンタル的にも幸せを得たいと。これ、普通のことだ。だからそれが普通になって欲しいというか、そうしたいということでお手伝いをしている。
一次産業、とりわけ農業に従事している方には積極的な方が少ない。能力はあるものの、どちらかというと内向的な人が多いというか…、逆に言えば積極的な方は都会に出て行ったり大企業に入ったりしてしまう。で、結果として少し引っ込み思案な人が地方に残るのだと思う。そういう方々が集まっているものだから、「発展していこう」という発想や価値観がなかなか出てこない。私はそういうところに入っていって、何かを見せたうえで体験して貰っている。一緒に考えて、一緒に商品をつくろうと。そういうことをしていくうち、現場の人たちも喜んで目の色を変えてくれる。
そうした小さな成功例をつくるとどうなるか。地方の人々は外をあまり見ておらず、隣の人ばかり見ている。だから隣の人が良い暮らしをはじめると、皆が「どうしてそうなったのか?」と考えるし、その真似もしたがる。そういう部分から変えていって皆が積極的になるような環境をつくるのが、地道ではあるが一番早いのかなと思う。
で、そのなかで出来た産品を、たとえば流通に乗せる、あるいはブランド化するというのもひとつの手だが、実際は加工したほうが流通しやすいし規制の壁も低くなる。また、国内だけで上手くいっても国内市場自体が少子化で縮小しているから、リーマンショック前ぐらいの儲けにしかならない。従って今は加工したものを海外へ運んだりしている。そこで我々が出店するというのもある。それと、ご質問にもあったが、私たちはだいぶ前から海外の人材を招いて教育等も行なっている。
そういった試みを通して、それでも成果が出ないという状況のなかで次に何をするか。吉兆としてはマーケットを求めて海外進出というのも考えているが、ただ出店するだけでは大きな利益を見込めないし、高級店の展開はリスクも大きい。それでクオリティが下がってしまうのであればやらないほうが良いと思う。それよりは、むしろベースキャンプのようなものを、たとえばナパバレーにつくる。そしてそこで加工品の物販をするといったアプローチが一番良いのかなと考えている。そこでお酒を含めた色々な商品をコーディネートしていくというのがひとつの方法としてあるだろう。

「日本人がメダルを獲れなくなるとしても、相撲ではなく、国際して“柔道”となるほかない」(大倉)
徳岡:そこに一次産業の従事者を連れていって、たとえば酒造好適米のような産品をつくっていきたい。そもそも日本人は適応能力が高い。北海道から沖縄まで全国各地に高級食材が溢れているのは、地域に合わせて勤勉に研究しながら色々なものをつくる力があるからだと思う。私たちはそういった人たちを年齢に関係なく連れて行って、向こうで研究開発を行いたいと思っている。辻先生のところとも一緒に開発出来るし、他の料理屋さんともコラボレート出来るだろう。また、その際は日本人だけでなく当地の、たとえばナパバレーであれば、地元ワイナリー等とも一緒にやっていきたい。
今年11月も農家の方々とCIAに行く予定だ。また、日本と違って海外では有名なシェフの地位や信用度が大変高い。従って、たとえばナパバレーにいるトーマスケラーという著名なシェフたちとも一緒に何か開発出来ないかなと思っている。そうしたシェフたちと、農作物の生産、それを使った料理、あるいはその物販といったことをチームでやっていきたい。それによって新しい可能性が生まれると思う。
あともうひとつ。農業の従事者だけでなく漁師の方も連れていきたい。たとえばあちらには海産品をアメリカ全土に届けるような流通網を持つトゥルーワールドグループという会社があるのだが、今、そこの出身者ともタイアップをしている。そこに漁師さんを連れていって、あちらで獲った魚を活き締め技術などを活用しながら有名レストラン等に卸していきたい。で、私はそこで料理をつくるのではなく、日本食材の営業マンになろうと思う。料理を実際につくるなどして色々とプレゼンをしていきたい。
将来的には養殖技術を持ち込みたいと思う。今は天然もののほうが良いと言われているが、自然界は汚染が進んでいる訳で、本当に天然ものが良いのかは証明出来ない。しかし養殖では水の質や水流、あるいは餌まですべて管理出来る。それならば砂漠のど真ん中で養殖を行って、ラスベガスに店舗展開することだって可能だろう。養鶏も同じだ。日本の鶏のもも肉はすごく美味しい。欧米ではむね肉を高い技術で美味しくするスタイルだが、そうでなく、もも肉をシンプルに炭で焼いていく。ワインと合うジューシーでオイリーなもも肉はあちらでも流行ると思う。そういったことを目指して養鶏所とともに高級な鶏専門店を展開していきたい。そこで地元のジビエを使うのも良いし、カリフォルニアのワインと合わせていくのも良いと思う。
大倉:技術の継承に関して外国人の方々を受け入れるというお話があった。私も大賛成だ。そうすべきだと思う。我々のアメリカ工場も社員30人ぐらいのうち日本人は5人程度だ。日頃のお酒づくりはすべてアメリカ人がやっているし、それで何も問題はない。何かトラブルが起きたときだけ日本人が行ってチェックする程度だ。
柔道はオリピック競技になって大変盛えたが、今は世界柔道連盟に日本人理事が一人しかいないと聞く。それで日本人がルールを決められなくなっている訳だが、ではそこで相撲のような道を選ぶのか。そうすれば普通の外国人は褌と髷を嫌うから相撲を選ばなくなるのだろうが、そういう道は現実的でないと思う。柔道のような道を歩もうとするならば日本人がメダルを獲ることが出来なくなる状況が来ることも恐れず、国際化していくべきだ。そうして皆が平等に競争するようになり、いつか「日本人が金メダルを取れなくなるかもしれない」といった現実が訪れたとき、徳岡さんのような人に頑張って貰いたい。そういった構図になるのではないかと思っている。
会場:養殖のお話も出てきたが、食の安全という側面で、植物工場というものに対するお考えが何かあれば教えていただきたい。(1:06:30)
徳岡:それも考えていこうということで、今年の11月、CIAへ行く予定だ。
会場:日本食を正しく理解をして貰う必要があるというお話もあったが、そもそも我々日本人がどこまで日本食の良さを理解しているのかとも感じる。その意味では食育も重要でと思うが、そこで企業が果たす役割は何かあるだろうか。
徳岡:やるしかないでしょ。待っていたら駄目ですよ。
楠本:…ロックンロールですね(会場拍手)。はい、時間になりました(会場笑)。実際のところ、食育分野も企業にとってはビジネスチャンスだと思う。
徳岡:ボランティアじゃなく、そこでビジネスに出来ないと物事は続かない。恋愛もギブアンドテイクでないと健全に育まれないし、それは親子関係でも同じだ。親がきちんと子どもに伝えることが出来ない限りリターンはない。「愛は大事」という話です(会場笑)。
楠本:「食は愛なり」と(会場笑)。では時間が来たので締めたい(会場拍手)。



























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)