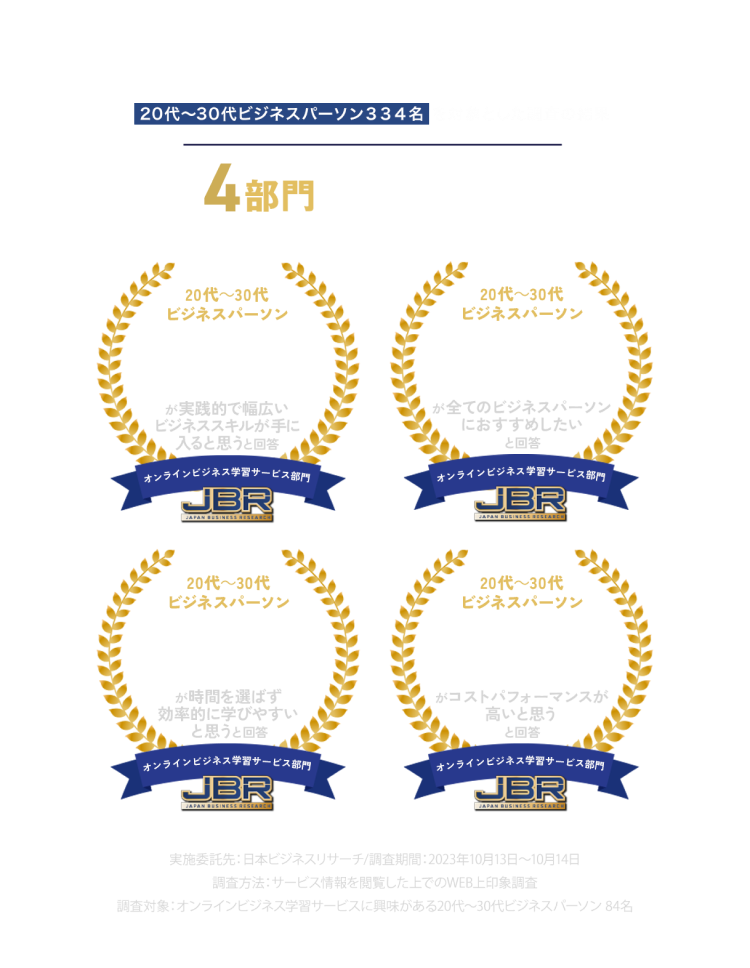「日本企業とグローバル企業の良さを掛けた“和魂異才”のハイブリッド企業が出て来ている」(程)
程:演題が堅いが、本セッションのテーマは端的には和魂洋才。アクセンチュアでは“和魂異才”とも言っているが。
パートナリングやジョイントベンチャー自体は以前からあったが、最近、これまでと違った形で日本企業とグローバル企業の良さを上手く掛け合わせた企業が出てきている。そこで今日は、自動車、エレクトロニクス、そしておもちゃという分野でそれぞれご活躍中の3名にお越しいただき、3社3様、いかにして和魂異才のハイブリッド企業、事業をつくってきたかを伺っていく。
まずは現在のアライアンス構成や、そこに至った背景などについて順に聞きたい。(1:41)
高塚:2011年7月にNECとレノボの日本国内PC事業を統合する格好で、NECレノボ・ジャパン グループを設立した。出資比率はNEC49%、レノボ51%で、NECパーソナルコンピュータ(以下NEC PC)、レノボ・ジャパンの2社をホールディングカンパニーが持つ形式。私はNEC PCの社長を務める。本来、ホールディングカンパニー会長のロードリック・ラピンが登壇する選択肢もあったと思うが、和魂ということでは私だろうとお鉢を頂いた。
日本という小さな市場でPCメーカー2社が一緒になるというと、多くの方は「むしろシェアの食い合いになるのでは?」と懸念くださる。しかし両社の製品価格帯とシェアを見てみると、NECが中間ぐらいの価格帯で高いシェアを獲得している一方、レノボは比較的低価格帯で戦っており、重なり部分は少ない。現在もNECはNEC、レノボはレノボのブランドで商品提供をしており、お客様には双方が認めて頂けていると思う。(6:10)
では合弁の狙いは何であったか。NECは30年にわたり日本市場でシェアNo.1を取り続けている。海外事業については、これまでトライアルはあったが、現況は国内に絞り込む判断をしている。なお企画開発からサービスサポートまで一気通貫にカバーしており、これは業界では珍しい。一般にはPC産業は水平分業が進んでおり、部品の調達量が多ければ多いほど安く出来るという構図がより顕著になってきている(これがグローバル市場への進出を加速する)。両社の調達量を見てみると、NECを1ならレノボはおよそ15。我々としてはその大きなボリュームを足すことでコストダウンを実現したいという狙いがあった。一方のレノボは、全体では世界シェア1位に肉薄しているが、世界3番目に大きな市場である日本において苦戦していた。ここでのシェア拡大がカギとなるが、日本のPC市場は世界的にも特異で、7割が日本企業勢に占められ、外資系はなかなか食い込めない。そこに風穴を開けたいという思惑を持っていた。(7:46)
高橋:私は1998年に日産の取締役になった。その後1999年に(カルロス・)ゴーンがやってきて、ルノーの事実上の傘下に入り、経営再建に至るプロセスを見てきた。そんな経緯から今日はお声掛けを頂いた。私たちの場合は救済「される」側であり、この会場にいらっしゃる皆さんはむしろ買収「する」側になることが多いと思う。そうした、見える景色の違いなども意識しながらお話ししたい。
日産とルノーとのアライアンスにあたり、ルノー側が挙げた基本的な考え方が以下の内容であった。「それぞれのアイデンティティ及び独立性の維持」「それぞれのブランドを尊重。いずれか一方のブランドを損なうかもしれないプロジェクトは採用しない」「アライアンス全体に利益をもたらす可能性があるプロジェクトでなければ採用しない」「ベンチマーキングによるベストプラクティスの共有」。これを最初に聞いた際には「随分と綺麗事を言うものだ」と疑心暗鬼が先に立った。コストカッター、コストキラーという異名も聞こえてきていたし、「実際には剛腕で一気に侵しに来るのではないか」と。ところが実際に動き始めてみると、彼らが本気でそう考えているということが行動を通じて理解されてきた。(10:35)
例えば一つの象徴として、日産側のアイデンティティを非常に尊重する組織構成が取られた。まずアライアンス・ボードの組成。ルノーの経営陣が日産に乗り込んでくるのではなく、私を含め日産とルノーでまったく同数からなるこのボードによって意思決定がなされる体制が作られた。さらにその下に、双方の知見を理解し、ベストプラクティスに倣って共同の成果を上げていくためのチームも多数作られた。それは、生産、技術開発、マーケティングといった機能ごとにメンバーが集められて互いの良いところを取り入れ合う「クロス・カンパニーチーム(CCT)」もあれば、ITシステムのように共通にインフラを強化するための「ファンクショナル・タスク・チーム(FTT)」もあった。そして、例えばディーゼルエンジンを統合しよう、など具体的なプロジェクトが発足すると、それを実行するための「タスク・チーム(TT)」が作られていった。こうした活動を通じ、共に動くのだということを象徴的に示し、本気で取り掛かっていったことがスタートとして良かったのではないかと思う。また私は、その際の経験を踏まえ「他社と組む際には言行一致ということがすごく重要になるのだな」と感じるようになった。(12:03)
なお、そういったチームに参加した社員に目を向けると、大きく成長した人もあれば、ついていけない人もいたが、結果として非常に鍛えられた。言語の問題もあったし、異なる会社の人々の中でどのようにリーダーシップを発揮し、自社の良いところを示していくかいうのは本当に大きな課題だった。(12:03)
三浦:タカラトミーは2006年にタカラとトミーの合併で生まれた。当時の国内おもちゃ業界ではタカラが2番手でトミーが3番手だったと思う。で、実は両社の仲はそれまで非常に悪かった。しかしこのままではどうみても1番手のバンダイに勝てない。グローバル化も進んでいるし、とにかく仲が悪い状態ではまずいから合併しようという話になった。そしてその1年後、アメリカのプライベートエクイティであるTPG Capital(以下、TPG)の日本第1号案件となった。CBO(Collateralized Bond Obligation)を含めて21%ほど持ってもらい、資本業務提携を行っている。(15:31)
当時はNHKで『ハゲタカ』というドラマをやっており、しかも玩具メーカーが買収されて悲惨な目に遭う逸話が描かれたこともあってファンドへの警戒は強く、当初は皆が大反対していた。ただ、なにしろタカラとトミーが合併した会社だ。どうも双方の立場を慮って遠慮し合うところがあって、当時は物事を力強く推し進めることが出来ない状態だった。その対策として第三者を入れ、経済合理性に基づいた意思決定をしていかれるようにしたいという狙いがあった。また国内では少子化が進んでいて、我々の業界もグローバル化は避けられない。それでグローバルなベストプラクティスを導入していくという意図もあった。(17:00)
その後2011年、東日本大震災の発生したまさにその日に、我々は米ナスダック上場のRC2 Corporation(以下、RC2)というおもちゃ会社を540億円で買収した。ただこれは、形式上は買収だが、実はその半年ぐらい前から両社で協議をしていた。そこで、「この業界なら4位か5位ぐらいまでには入っていないと恐らくは生き残れないね」という話になっていた。で、「一緒になれば出来るかもしれない」と。ではどうやって一緒になるかという段階で、「タカラトミーのほうが一応大きな会社なのでRC2を買収する形にしよう」という話になったという経緯がある。実際、一緒になってどうだったかというと、グローバル化という点ではアメリカ企業のほうが相当に進んでおり、我々が教えるのが30%に対し、先方から教えて貰うのが70%という感じになっている。(18:08)
合併をしたり、ファンドを入れたり、あるいはアメリカの会社を買収したり・・・経緯を見るとかなり荒っぽく感じられるかもしれない。ただ、これはおもちゃ会社の特性とも関係がある。タカラもトミーも同様だが、元々創業家というのがいる。また、どうしても開発側が強くなってしまい傲慢になりやすいという面もあった。だからときどき異なるカルチャーを入れて内部を揺すぶり、異なる取り組みを外的に強いられないと会社自体がもたないという危機感があった。(19:50)
「買収先のやり方を尊重したうえで効率化する、だから誇り高きIBMマンも残った」(高塚)
程:財務面やコスト競争、企業文化のことなど、3社3様の危機感が背景にあったことがうかがえた。一方では合併にあたり、選択肢として日本企業とのパートナリングもあったと思う。なぜグローバルな海外企業と組むことを選んだのか。(20:48)
高橋:要するに追い詰められていたのだと思う。当時の日本がどんな状況だったかといえば、アジア経済危機で銀行は駄目だったし、現在のような産業再生機構や産業革新機構もなかった。経済産業省も経験もないということで日産のような巨大企業の救済に乗り出さない。それで、とにかく生き残るためには外資とのパートナリングしかなかった。そもそも自分は、日産がおかしくなった頃、部長だったが、自分の勤め先に今月のカネがないということすら知らなかった。社員に心配をかけない、それは役員の責任ということで、トップから情報が落ちて来ていなかったのだ。(追い詰められるところまでいかないという意味では)情報をどの時点でどこまで出すかということには問題意識を持っている。(21:48)
高塚:パートナーに日本企業をという選択肢は、情緒的に考えればあったと思うが、とにかくPC業界では水平分業が進み、規模の経済が勝敗に影響する側面が強くなっていた。そこから考えると、当時の富士通や東芝と仮に合併していたとしてもレノボ単体の調達力には届かなかった。従って、やはりグローバル型で、かつNECの十数倍という調達力を持つ企業が選択肢に入ってきた。
そのうえで、なぜデルやHP、エイサーではないかという意味では、北米に元々IBMということで強い基盤を持ち、中国などの新興国で伸びており、そして特殊性を持った日本市場での急速なシェア上昇を考えているレノボというパートナーで話が進んでいった。(24:34)
程:タカラトミーのRC2買収については、そもそもTPG(ファンド)とタカラトミーのどちらから出た話だったのか。
三浦:双方からだ。特にファンド活用は初めてという人間が多かったし、信頼関係がないと出来ないことなので1年ほど時間をかけて話し合いながら進めた。RC2の買収には社内での危機感の醸成という意図もある。おもちゃ産業は夢を売る産業だから、基本的には皆が楽しそうに仕事をしている。ただ、そのために危機感があまりない状態になってしまっていた。そこでトミーとタカラがまず合併を行い、5年後にはある程度収益が上がって無借金にはなったのだが、それでまた危機感のない会社に戻ってしまっていた。そんなこともあって、財務の許す限り一番大きな借金をして買える会社と一緒になろうという話になった。(26:59)
TPGに関して言えば、彼らと組んだおかげで一番楽になったのは買収のところだ。我々からすると、これほど大きな買収を行うのは10〜20年に一度という感覚だが、彼らはそれが本業だから比べ物にならない数の経験を持っている。日本企業の多くは一度決めたらどうしても前のめりになってしまうところがあって、「少しぐらい高くても、まあ買ってしまおう」となるところで、お金にうるさいファンドがブレーキの役目を果たしてくれた。その一方で、「この値段だったら恐らく行ける」という判断もしてくれた。なかなかアクセルを踏めないところで思い切るために良かったと思う。(28:36)
程:ハゲタカとまではいかなくとも、外資に関しては黒船といったイメージもある。そのイメージと、実際に仕事を進めたイメージのあいだに違いはあっただろうか。(29:28)
高塚:我々のジョイントベンチャーは2011年7月に発足したが、その後、箱根のホテルに双方の事業部長クラスが集まる機会があった。一方の席にはレノボ・ジャパン、もう一方の席にはNECの幹部が並び、そこで会長のロードリック・ラピンがある質問をした。レノボ側には「自分が最初に勤めた会社がレノボ・ジャパンであるという人は手を挙げて欲しい」と言ったのだが、誰ひとりとして手を挙げなかった。そして今度はNEC側に「NEC以外で働いたことのある人は」と聞いたのだが、これにも誰ひとり手を挙げなかった。私はそのとき、「これは大変だな」と思った。
つまり大切なのは、いかに違う人たちが集まっているのかをまず互いに認識すること。そして、違いの認識に基づき、言葉の共通化を図り、具体的にプロジェクトを進めて目的を達成する中で、確かに違うところから集まってきた人たちなのだけれど、前に進む中で違和感も解消できるし、信頼感も醸成されるね、ということが確認できた。(30:26)
高橋:当初は確かに「外国企業の金がつぎ込まれたうえで人がやって来る」ということ自体が嫌だと言う人は大勢いた。幹部クラスで辞めていった人がいたのも事実だ。まぁ、我々の場合、やってきたのはフランス人だったので“黒船”とは少しイメージが違ったが(笑)。
乗り越えられたのは先述した組織構成によるところが大きい。9人の取締役会メンバーは必ず5人が日本人、そして4人がルノーからの人間で構成されていた。ちなみに今は9人のうち5人が日本人なことは変わらないが、4人の外国人のうち2人は日産の人間で、ルノー側はゴーンともうひとりだけ。いずれにせよ、そんな環境でディスカッションを行う場が物理的に増えていったことで「これは要するに文化の差なのだ」ということが次第に理解出来るようになっていった。(33:23)
同じことが幹部だけではなく、実行部隊でも起きた。クロスファンクショナルチームの組成により、内側にある壁をすべて壊そうとした訳だ。たとえばなんらかの営業問題について提案させようというときは、そのメンバーは…、大将は営業部長や営業課長だが、それ以外は他の部署から来た人間にしていた。そこで価値観や経験の異なる者同士、喧々諤々させることで内側から変えていったのだ。そのなかで外国人に対する柔軟性もひとりでに培われていったのではないかと考えている。(34:48)
どういった場合でも最初はどちらかが黒船になる。ただ、もしそのときに自分たちが乗り込んでいくほうとなるのであれば、先ほどお話しした通り、とにかく言行一致で真に相手のベストを引き出していく。どんな買収でも、良いところがあるから買うのは間違いない訳だから、その良さを認め、引き出す姿勢をきちんと前面に押し出していけば相手も変わると思う。(35:50)
程:レノボは中国企業だが、IBMのPC部門を引き継いだ経緯から考えれば、ある意味ではグローバル企業としての色彩のほうが強かったのではないかと想像するが。(36:21)
高塚:仰るとおりだ。合併によって我々はグローバルの一員にもなったので、サンフランシスコで開かれるリーダーシップ会議などにも参加するようになった。行ってみるとメンバーの国籍比率は予想とまったく違う。メディアには「レノボ(聯想集団)=中国企業」と書かれるが、中国人はせいぜい10%ぐらいで、それ以外はあらゆる地域から人間が来ている。完全に多国籍企業だ。中国と日本、という二項対立ではないので、我々が入っていくことに関してあちら側は違和感を持たないし、こちらも何か一つの文化、様式に合わせようとするのでなく、日本は日本の良さをきちんと見せればいいという姿勢でやってこられた。(36:45)
ご指摘の通り、レノボはIBMのPC部門にいる人々を全て引き受けた。「ThinkPad」というトップブランドを創出してきた人々だ。誇り高きIBMマンのことだから、きちんとした扱いをしなければ黙って去っていってしまったのであろうことは容易に想像がつく。レノボには、自分たちのやり方を押し付けるのではなく、その国、もしくはそれまでIBMが展開していた地域で採用されていたやり方を尊重したうえで効率化する。そういう文化があり、だから開発やマーケティングの貴重な人材を留められたのではないかとも思う。(38:00)
「コントロールよりインフルエンス、それが最終的には成果につながる」(三浦)
程:一般には、他社に資本投入する際、ブランド以外のものは“がちゃん”と混ぜて共有化し、一気に効率を上げる企業が多いと思う。しかしそういったハードなインテグレーションに対し、お三方の関わった事例ではソフトなコンソリデーションが目指されたように感じた。功罪あると思うが、どうか。(39:27)
三浦:当社の場合はRC2買収前にタカラとトミーが一緒になった際の経験が生きたと思う。当時のタカラは大変良い商品を出していたが、経営のほうはがたがた。だから世間的には対等合併と言われていたが財務的には救済合併のような形だった。しかしそこで我々が「救済合併ですよ」と言って進めてしまうとタカラの成長のDNAが失われてしまう。だから我々経営陣も「2年ぐらいは混沌としても構わない」「トミー流を押し付けるのではなく新しいやり方を探していこう」という話をしていた。それで随分と苦労も遠回りもしたが、それが結果的には良かったと振り返っている。だからRC2合併でも同様の姿勢をとっている。特に生産工程等についてはおもちゃに対するフィロソフィーが両社でなかなか合わないところがある。工場の閉鎖などの判断はスピード感を持ってやるにしても、(両社のアイデンティティに関わるような)そういうところには時間をかけていく。(41:08)
高塚:先ほど高橋さんがご説明されたのと同様の2社を横断するファンクションが弊社のケースでも作られた。「ブランドと関係ない部分についてはだんだん統合していきましょう」というコンセプトのファンクションだ。で、それを誰に担わせるのかという段階で、会長のロッドは各部門のヘッドが両社で同じ数になるよう、大変気を使いながら組織をつくってくれた。そこでもし全部門が片方の会社になっていれば、「結局、思い通りにやろうとしているだけではないか」という風に受け取っていたと思う。実はレノボ・ジャパンのコールセンターは現在NECで請け負っているのだが、「レノボのコールセンターは顧客満足度No.1のNECがやっているので安心」などと言い、そういった重要なファンクションにNECの人間をアサインしてくれていることも、「大事にされている」という実感につながっている。(42:43)
程:分野によっては「ここは自分たちのほうが勝っている」という部分もあったと思うが、その辺で駆け引きのようなものはなかったのか。(45:25)
高橋:当初、私はゴーンに「とにかくフランス工場へ行って来い」と言われた。それで恐る恐る行ってみたのだが、結果的には日産のものづくりを教えるばかりだった。自分たちのやり方を押し付けるために私に工場に行けと言ったのではなかったのだ。逆に、当時のルイ・シュバイツァー会長が「日産のここが強い」といったことを現場に徹底的に伝え、日産のベストプラクティスを受け容れる素地をつくっておいてくれたのだと思う。そして素直な目で個々に見ていくとルノーにも良いところがたくさんあった。同じように努力しているのだから当たり前だが、とにかく、そのようにして両面からベストプラクティスを追いかけていくのが良いのだなと当時は感じた。(46:20)
程:フロアにいらっしゃる方々も、今後、上手く外資の力を使っていかなければならない環境に遭遇するかもしれない。そうなったときのアドバイスが何かあれば。(48:18)
三浦:端的に言うと「コントロールでなくインフルエンス」なのかなと感じている。アメリカで我々が話をした相手は、教育レベルも目的意識も非常に高い人ばかりだった。そういう人々に、「日本のヘッドオフィスがこう決めたからその通りやってくれ」などと言っても面白くないと思われるのが関の山だし、モチベーションも下がる。やはり、「こういう理由でこうなっていて、そちらのほうは恐らくこういう環境だから」といった風に議論を重ね、気持ちを動かすプロセスは必要と思う。面倒ではあるし、言葉も違うので、「決めた通りにやれ」というコントロール型に陥りがちであることもわかるが。(48:55)
高橋:まず文化の差があると認識するべきだ。いつも思うのだが、日本人は常に「チーム感」を持って仕事をしている。場を中心にし、大事にする。そういう人々は、部なら部という固まりで、決まったことを実行するぶんには非常に強い。けれども海外の人たちは個人主義だ。「個人の資格」というものを大事にしている。発言を聞いていれば腹の立つこともあるが、「彼は自分個人の資格の発想で言っているのだな」と理解しておくことが肝要だ。だからパーティーが大好きで、同じような資格同士で集まる。サッカーなど見ていても、彼らは資格。キーパーはキーパーの中で誰が上手くて、認められているか、という見方をする。同じ感覚がクロスファンクショナルチームなどでも如実に表れる。そこを自分たちと同じようにしてくれと言って変わるものではないわけだから、こちらも両方を身につけていく。そういう努力が重要なのかなと思っている。(50:12)
高塚:一言で表現すると「違うということの認識」だと考えている。日本人同士なら問わず語らず「だいたいこんな感じ」というものがあるが、そうならないことに対しても嫌悪感を持つべきではない。見ている側面や範囲、場所が違う点を踏まえ、「私はこういう部分を見ている」と、きちんと話していく。違和感を放っておいても何もはじまらない。出資比率などに過度な影響を受け、臆したり、気を使って黙ってしまうべきでもない。片方が何か主張することが、即オーダーということではない。彼らは考えを述べているだけなのだ。手法は色々あると思うが、とにかくそういったコミュニケーションのなかで合意を作っていくことで、目標がきちんと設定され、同じところに向かって進んでいくことが出来る。(52:20)
ところが日本人はぎりぎりまで黙っていて、そして「何か言え」という段になると突然怒鳴ったりする(会場笑)。これは日本人の悪い癖だ。別に喧嘩をしろという意味ではない。「ある部分には賛同するが、ある部分には違和感を持っている」というのであれば、何故かをきちんと伝えるという意味だ。そうしたスタイルを日本人は持っていないかもしれない。しかし海外の方とコミュニケーションをするのであれば、ときには相手に通じるスタイルへシフトするということも大事になると思う。(54:35)
「現場でこそ自身の知恵が煌くと信じる。日本人の心のふるさとは地上にある」(高橋)
程:冒頭で“和魂異才”という言葉を使ったが、最後に和と洋の部分でひとつずつ、「これは互いに持ち寄るべき良い価値観ではないか」というのがあれば教えて欲しい。(55:31)
高塚:高橋さんも仰っていたが、あちらはキーパーならキーパーというように、ファンクションとして個人の能力を高めるという部分に大きな目的意識を持っている方が多い。一方、日本人は一連の流れのなかで物事を上手く運んでいく方法を考える。お客さまが厳しいだけに、「顧客にご満足をいただけるよう全ファンクションで協力しよう」という話なのだと思う。欧米に比べてより長い時間を同じ会社で過ごすこともあり、会社そのものがお客さまを満足させなければいけないと考えるのではないか。そういったお客さまを大事にというところは和にして、あとはそれぞれのファンクションとして果たす役割を最大化するために洋でいく。そういった考え方でトータルアウトプットを高めることが和魂洋才なのかなと感じる。(56:17)
高橋:日本には現場の良さがあると思う。自身の少ない知見ではあるが、日本人ほど現場を大事にする経営者はほかの国であまりお目にかかれない。ゴーンはそういうところをよく分っていたから徹底して現場を巡った。そういった精神、あるいは「現場へ行くと自分の知恵がすごくよく煌く」というような感覚は、和魂のひとつの原点ではないか。あるインド人は、「西洋では心のふるさとは天にあるが、日本人の心のふるさとは地上にある」と言っていた。その辺の感覚は皆さまもお分かりになると思う。これは現場を大切にする考え方の原点ではないか。私も現場が好きだ。これはどこへ出掛けていっても持ち続けて欲しいと思う。そして洋だが、先ほどは資格と表現した。これはある意味で、天命というか、「自分はこういうことを自分のものとして持つのだ」という分野を必ず持っている。私としてはその両方を身に付けることが和魂洋才ではないかと思う。(59:03)
三浦:経済合理性では洋のほうが相当進んでいると感じるが、それが企業経営のすべてではない。特におもちゃ産業に関して言えば夢を売る産業なので、それをどのように実現していくかという部分も大事になる。これは合理性では証明出来ない世界だし、我々としてはそういった部分を大事にすべきだと感じている。(1:00:00)
質疑応答
・幹部やスタッフが異文化を受け入れるためにした取り組みや仕組みは?(1:00:04)
・言葉の問題はハードルとなったか。どのように克服したか?(1:01:28)
・グローバル企業が合併後に日本企業の良さとして社内で採用したものは?(1:01:59)