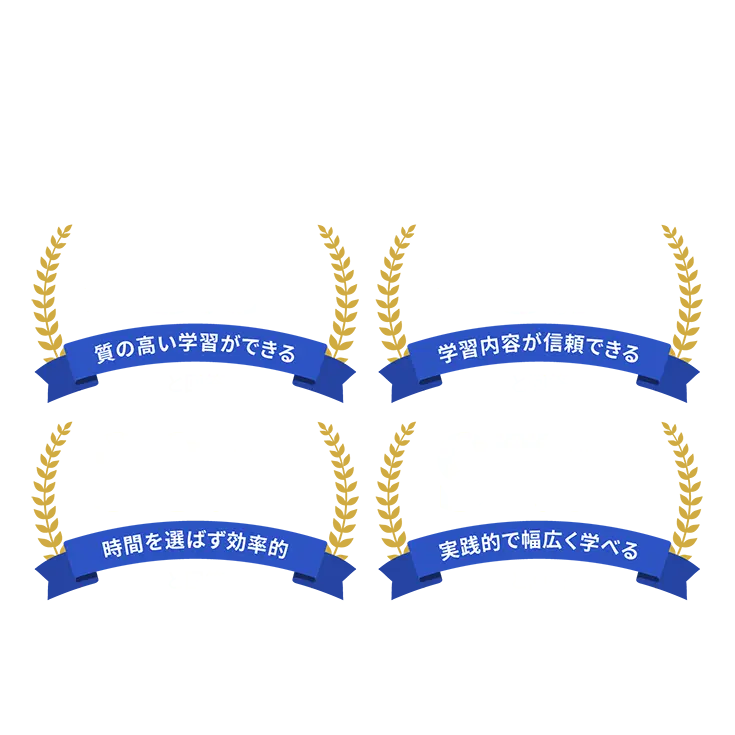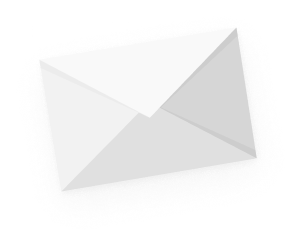第2回あすか会議の最終セッションには、産業再生機構COOの冨山和彦氏、元・カネボウ社長の小城武彦氏をはじめとする「事業再生のプロ」が集結。現場の事例を生々しく交えながら、「経営者は合理と情理のどちらからも目をそむけてはならない」(冨山氏)と、骨太の議論を展開した。議論の全容を詳報する(文中敬称略、登壇者の肩書きや発言は開催当時のもの)。
「不満が表面に出るのは健全。厄介なのは水面下で動く抵抗勢力」(星野)

■組織はヒト、という。ではヒトの力を引き出すリーダーシップとは、どのようなものなのか。企業再生の現場にフォーカスして聞いていきたい。パネラーの皆さんは、第三者の立場から経営再建に入っていくという経験をしている。そこで、外から火中の栗を拾いにいく難しさやメリット、困難を越える方法論などから、まず聞かせてほしい。
小城 私は、産業再生機構から落下傘でカネボウに入ったが、内部からの抵抗は大きく2つに分けられるように感じた。
1つは、年功序列に代表される、老舗企業ならではの企業文化によるものだ。40歳代というと通常は課長クラスであり、それと同年代の社長が来たとなれば、拒否反応を起こす。もう1つは、ヨソモノへの抵抗感。カネボウは生え抜きの社員が多数を占めており、仲間意識が強い。
加えて、「社長」という立場の人間に対するイメージが非常に悪いということもあった。前社長はいわゆる“御輿に乗った”タイプの人物。短期的にはそれでも組織は回ってしまうわけだが、そのせいで、社長というものに対する猜疑心が社員の心に植え付けられてしまっており、自分もそういう先入観を持って迎えられた。
逆に外から入っていった強みは、「この会社を再生させることが自分の役割、ミッション」ということがはっきりしていたので、それ以外のことは気にせず、腹を括ってかかれたこと。自分自身、元来、カラッとしたキャラクターではあるので、変だと思うことは、「これって、おかしいですよね」と全部、口にしてやってきた。
後藤 ユニゾン・キャピタルから東ハトの再生に入った。まだ若い自分が選ばれたのは、マーケティングとコンサルティングの両方を経験している人間が珍しかったからだと思う。最初は経営企画担当の執行役員として入ったが、簡単に言えば何でも屋。東ハトはオーナー企業で当時、執行役員は皆50歳代。33歳の自分は異分子、外国人扱いされた。受け入れ側にしてみれば、「こいつの話を、どこまで本気で聞いていいのか分からない」「どうせ3年で抜けるんだろう、信用できない」という感じだったのだと思う。
小城さんの話にもあったが、私も、問題があると思ったことは全て口にしてやってきた。生え抜きの社員が常識としてやっていることの中には、一般的な社会通念から見たら、全然、常識ではないこともある。それを、「なんでですか」「どうしてですか」と、ひたすら疑問を伝えていった。問題の本質に迫るまで、5回でも6回でも「なんでですか」を繰り返すので、「なんでボウヤ」と呼ばれるようになった。そうこうするうちに、「仕方ない(応えてやろう)」というような、社内に置けるキャラクター設定ができていった。
ヨソモノが信頼を得るには、とにかくコミットすること。朝は誰よりも早く行って、夜は誰より遅く帰った。それを続けることで、「本当に(この会社を)良くしたいのだな」と感じてもらえるようになったと考えている。
星野 温泉旅館業というのは極めて特殊な世界だ。形式的に上から入って「どうぞよろしく」で、すんなり始まるわけではない。
私が考える2種類の抵抗は、「表に出てくるもの」と「水面下で進むもの」。前者は議論の場などで出てくる抵抗勢力で、これはある意味、健全。真っ向勝負で対応できる。問題は後者。表向きは合意しているのに、現場に行くと何も進んでいない、進ませない。これが危険だ。
後者を止めるため、私の場合、再生プロセスの最初の1年は、従業員全員が一致する利害に集中することにしている。例えば、「高収益を目指そう」というのは生活に直結するから反対のしようもないし、「お客様に褒めてもらえるようになろう」「給与を上げよう・休みを増やそう(そのために生産性を向上させよう)」も同じ。
とにかく議論が表に出てくるように、出やすいようにする。目的さえ一致すれば、あとは方法論だけの話だから、大変に進めやすくなる。経験的には、それで結果を出せば、2年目、3年目はおのずと上手くいく。
冨山 再生が上手くいくか否かは「危機感があるか」にかかっている。ヒトは変化に抵抗する。野球をやっていた人に、明日からサッカーをやれ、というようなもので、古くからいる人ほど、それまでやってきたことに固執する。
中小企業は規模が小さい分、経営状態を肌で感じやすく、また、大企業に対して元々、ハンディキャップがあるのを分かっている分だけ、危機感が生まれやすい。ところが、カネボウ、ダイエークラスになると、客観的には明らかに破綻しているのに、危機感はなかなか生まれない。沈みかけのタイタニック号に乗っているようなもので、外に投げ出された瞬間、10秒で死ぬ、みたいな状況なのに、船の中ではまだ席次とかを決めている感じだ。そこで、どれだけリアリズムを持たせられるかが一つのカギだ。
再生機構は国が関与してしまっているから、ますます厄介で、うち(再生機構)が入っていった瞬間、「もう、これで大丈夫だ、救われた」みたいな空気感になっちゃう。
現場はまだ良い。最先端でドンパチやっているから、負けが込んでいるのは肌で知っている。問題は、40歳代、50歳代、高学歴の中間管理者層。もともと頭の良い人たちが、腐りかけた組織で年齢を重ねてきているのが一番、手に負えない。見た目は従っているのに、腹の中では背いているというか、ムーンウォーク攻撃に出る。顔とカラダはこちらを向いているんだけど、動きとしては後ろに下がって行っちゃう(笑)。これをどうするか。
先ほど、星野さんが「誰もが一致する利害に集中する」と言われていたのは私も賛成で、有効な方法論の一つと思う。ただ、それだけではダメで、“生け贄”が必要なケースもある。もちろん、ここに一般解はないので、(誰かのクビを切って見せしめにすれば、どこでも抵抗勢力がおとなしくなる、などと)ミスリードはしないでいただきたい。座敷ごとに、何がウケるかは、まるで違うし、再生機構が抱えている41案件でも全て、個々の性質に応じた方法論を取っている。例えば、ある会社では、危機感はあるものの、変にいじけてしまっていたし、別な会社では、まだ全く危機感がなかった。怖いのは、こういう人達を頭から否定すること。ゲリラ戦が始まり、思いも寄らないところで、自爆テロをやられたりする。階層ごと、企業ごとに異なる状態や想いに肉薄し、誰を元気づけるか、適切な判断が必要となる。人間的な洞察力が低いと、内側から壊される。
「ナカタの執行役員就任が社員の心に火を灯した」(後藤)

■ケースバイケースの対応が肝要とのことだが、カネボウ、東ハトなど、それぞれに課題をどう捉え、具体的にどのようなアプローチで再生を進めたのか。
小城 私が考えるに、日本の組織には?帰属型と、?参加型がある。前者は、終身雇用を前提とし、社内で自分のキャリアを作っていくという社員の多数を占める組織で、後者は目的ありきで入社し、それが達成された暁には他社へ移ることを前提とした社員が多数を占める組織だ。カネボウは前者であり、ここから先は、その前提を持ったうえで聞いていただきたい。
カネボウで、私が最初にやったのは、企業理念の作り直しだった。企業組織の最上位に立ち返った。目的は3つあり、1つは「問題意識の視座を上げること」。もう1つは、作業を通じて「私自身がカネボウという会社(のローカル言語や文化)を理解すること」。そして「反省論を造る~自然と反省論が巻き起こるようにする~こと」。
カネボウの企業理念には、「上司のほうを向くな、生活者の目を持て」とか「現場、現実、現物に質問しつづける」とか、非常に良い内容がたくさん入っている。これを、「本当にそのとおりにできていたか?」と問い直す課程で、中間管理層は反省を強め、現場は会社を好きになる。そうやって改めて掲げなおした企業理念を、「今度はやり抜く」と宣言してもらった。
次に、マネジメント層に、「仕事をする」ことの具体的な意味を理解してもらうことに注力した。以前の経営陣が悪いモデルを示していた影響が残っており、下から積み上げてきたものをただ「演じる」ことが仕事であると勘違いしている人が特に上位層に多かった。これを直すこと、ラインマネジメントの活動量を挙げ、スタッフの仕事量を減らし、浮いた人材を顧客接点に振り向けることを率先して実施した。例を挙げれば、内部の想定問答作成などを大幅に簡素化した。「そんなものは、幹部が自分の反射神経で答えるべきもの。本来必要なし。」という具合に。
自分に与えられた時間は、わずか1年強だったので、徹底的にハンズオンの姿勢を貫いた。本社の経営会議だけではなく、各事業部の経営会議、その下の商品開発会議や営業会議にも全部出席し、価値を生まない仕事の選り分け、上長のあるべき姿というのを見せていった。
現場の従業員に対するコミットメントとして、とにかく現場にも足しげく通った。ダメな経営者は現場に行かない。1年3カ月で泊まりがけの出張が100回を超えた。
後藤 東ハトは中小企業で、かつ1度、倒産している(編集部注:東ハトは、日本初のプレパッケージ型民事再生のケースであり、ユニゾン・キャピタルが請け負った)。このため、私が入った時には危機感を通り越して、絶望感に溢れている感じだった。そこに、36歳社長が入ってきて、その下が33歳のボク。ホントに大丈夫なのかなぁ、という感じだったのではないかと思う。だから最初は、「みんなで再生させよう」「元気になろう」とモチベートしていった。具体的には、とにかくマーケティング重視。良いイメージ、ブランドを再構築することに注力した。ナカタ氏(中田秀寿氏)は、そこに共鳴してくれた。
彼が執行役員として参加したことで、取引先など外部に向けても良いイメージを発信することができたが一番、効果があったのは、社員に対してであった。初めてナカタ氏が執行役員になると社内に案内をした際のことは忘れられない。最初は皆、ピンと来ていなくて、「九州支店にナカタヒデオってヤツがいるけど、あいつが役員になるわけ?」みたいな感じだった。それが、“あの中田秀寿”と分かり、大歓声が上がり、しかし、すぐに「なんで、うちなんかに…」といぶかしがる声が出た。そして次にそれが、実感として腑に落ちてきたときに、「ナカタが来てくれるぐらい、東ハトは本気でやろうとしているし、やりきれるんじゃないか」という雰囲気が社内に染み渡った。
マーケティングのセオリーに則ったことも、もちろんやった。100以上あった商品数は、30種類まで切って、収益性を高めた。幸い、キャラメルコーンのリニューアルや暴君ハバネロなどのヒットがあり、売上もついてきた。
一方、企業風土を変える取り組みにも力を入れた。旧・東ハトはオーナー企業で、社員は上に絶対服従。右向け右の世界で、灰皿を投げられ、避けたら避けたで、「なぜ避ける」と叱られるような企業文化だった。こういうことが続くと、社員は間違ったことが目の前で行われていても抵抗しなくなる。それは実行力のない組織という意味ではなく、現場は「やれ」と言われたことはモーレツな勢いでやる。ただ、その理由が「オーナーに言われたから」なのだ。そこを、「なぜやるのか」をはっきりとさせる、自主性を重んじる風土に変えるところに、すごく時間をかけた。
例えば私は、60人近い社員に会って、膝詰めで話をした。…と言っても、辺見さん(辺見芳弘・社長)は全員に会ったようなので、自慢にはならないが。工場など現場をまわると、「経営の人が来てくれるのは初めてです」なんて言われたりする。会ったことのない社員の名前を名簿の写真で覚えていって、現場で声をかける。そうすると皆、驚いてココロを開いてくれる。
オーナー企業のため、利益の数字は出てこないし、売り上げにもウソの数字がある。情報公開を積極的にすることで、そうした悪しき慣習にもメスを入れた。
星野 冨山さんが言われた、40-50代の社員は抵抗勢力が多いというのは確かに実態としてある。私の経験上も、そういうことが多い。ベストソリューションは、「辞めてもらうこと(メンバーが入れ替わっていくこと)」と、私は思う。メンバーが入れ替わったところで、従業員数200人や300人(のリゾート施設)であれば、現場に混乱は起こらない。
変革における組織の動かし方はトップダウンが基本だ。仕事のやり方、プロセスはトップが決めて、中身のところはやる気のあるスタッフに自由にやらせる。その傍らで抵抗勢力はバサバサと斬る。それがトップの役割と思う。例えば、ゴールドマン・サックス+星野リゾートで再生に入った古牧温泉のケースでは、従業員500人中60人もの管理職がいた。そもそも、なぜ温泉旅館に部長やら課長が必要なのか、そこまで階層を細かく区切ってどうする?(ちなみに星野リゾートでは3階層)という感じではあるのだけれど、とにかく最初の段階では少々不自然でも気にせずに60のユニットを作って、管理職全員を現場の責任者にした。そのうえで、4カ月の期限付きの目標を持たせたところ、自然に40ユニットまで減った。逆に言えば、20ユニット分のリーダーが退いていったことになる。見方によっては、これは“斬るための手段”であったかもしれない。ただ、それをできる限りフェアなシステムで行うことがポイントと考えている。
「ヒトを斬るのではなく自ずから退出していく仕組みを創る」(小城)

■会場にも再生に取り組む経営者がいるはず。事例を共有してもらえないか。
会場 当社は、創立30年の企業で、社員の大半は大卒のエンジニア。エンジニアなので皆、凄くピュアで、いわゆる“良い人”。ただ、言われないと動かない、というマインドセットが困りモノだ。良い人だけに切りづらいが、やはり、For the Companyが前提。切らなきゃならないのだろうなぁ、などと、今日の話を聞いて思った。
■ヒトを切るメリット・デメリットというのは、必ずある。会場からのコメントのように、デメリットが目立つ場合、経営者としては迷うはず。パネリストの皆さんは、どう判断してきたのか。
冨山 先に遡上に挙げた高学歴の中間管理職というのは、オペレーションを人質にとって脅してくる。「オレが辞めると、こんな障害が起きるぞ」とか「100人はオレに続いて辞めるぞ」といった具合だ。実際には、人望のない人ほど、そういうことを言うケースが多く、部下が1人も辞めなかったりするのだが、インテリ優等生の経営者は、そういう脅しを受けるとブレる。ブレている気持ちが顔に出てしまったりもする。でも、そこでブレては絶対にダメで、試されていると思わなければならない。実際、中間管理職をドッと切れば、短期的には組織全般としてのパフォーマンスが下がるのは、それは当然のこと。でも、そこで経営者がブレると、総崩れになる。
現場視点も大切だが、将棋で言えば、例えば「小城クン」というコマがあって、対抗勢力のコマがあって、それらの動きを現場視点、当事者視点で見るだけではなく、どこか客観的に盤目全体を見ている自分がいるようなそういう視点(鳥の目と虫の目の使い分け)がなければ務まらないし、反応を誤る。
カネボウ化粧品のケースなんて、大変。従来、社長といえばプロパーの、60代の社員がなるところ、ゴッソリ上を切って、中から40代の社員(編集部注:知識賢治氏)を引き抜いた。パラシュートで40代社長を入れるだけでも軋轢はあるのに、プロパー社員1人を飛び級させるのだから、それは、とんでもない暴挙で、脅しだってある。それでも、やると決めたことはやる。
会場 ここまでの話を聞いていて感じたのは、「バサバサ斬る」と言葉では言っても、やっていることは、「(辞めるべき社員が辞めていくための)仕組みづくり」であるということ。社員本人が自分で答えを出すように誘導している。それが表れとしては「バサバサと斬った」に見えるだけなのだな、と。
小城 全く仰るとおりで、大体、自分で人員削減の矢面に立ったことのない人ほど、「斬ればいいじゃん」と軽々しく口にする。そんな人には、きちんとした人員の削減などできないと思う。頭のいいヒトは自分がどう評価されているかということは、きちんと理解できるから、仕組みさえ作れば自然と降りていくし、または、しっかりと対話すれば半分は古いやり方を変えて残る。方法論は幾つもある。どれを選ぶかは、もちろん、そう簡単なことではないが。
冨山 現場の経営者には「東に進みたいのに西に行かなければならない」という時がある。例えば小城クンは、再生機構ではある時期、評判が悪かった。裏切り者扱いされた。それは、どうしようもないオッサンを本気で救おうとしていたから。でも、これは経営の非常に逆説的で難しいところなのだけれど、本気で救おうとしないと本気で斬れない。再生機構側、即ち株主側の立場では、800万円の年収を得ているヒトは、800万円分の営業収益を上げてくれなければ困る。800万分、稼ぐか、稼げないなら辞めるか、どちらかなのだけれど、そこが経営者と株主の阿吽の呼吸が必要なところで、お子サマ投資家だと、そこを理解できずに(小城さんのほうを)斬ってしまう。企業再生の舞台には、そうしたパラドックスが沢山あって、例えば、短期間で組織を変えるためには、俺たちは永久にやり続けるぞと本気で思って、本気でそう言わなければならない。
小城 株主が出す論理的・合理的な結論に対して、現場がどうしても心情的に納得できず、強烈に対立せざるを得ない場合がある。そのときに、株主から派遣された社長はどのように振舞うべきか。 私のスタイルは、結論がどうなるにせよ、徹底的に現場に入り込み、彼らの希望をかなえ、彼らを守るように本気で血みどろになって戦ってみる。それをしていれば、仮に結論が株主の言うとおりになっても、「そこまで社長がやってくれたのだから、仕方ない」と何とか現場も理解をしてくれると信じている。最初から株主と同じ歩調をとってしまうことは簡単なこと。でもそれでは、「帰属型」の会社の経営はできないと思っている。
そういうことが分からない投資家が企業再生に入ると上手くいかない。カネボウの時には、冨山さんはそこを分かってくれていた。
後藤 東ハトもファンドが入っており、営業のナントカ部長のレベルまで個々の社員の情報は伝わっている。私の場合は「○○というふうにして」と伝えたことが、その下の社員にきちんと伝わっているか、実行されているかを確認する形、即ち事実ベースで追い込んでいったのだが、ファンド側からは「なんで、すぐに変えないの?」と、やはり言われた。それでも自分のやり方は通した。1年半かかったが、最終的には辞めてほしいヒトは皆、自発的に辞め、今は昔、グループ長だったヒトが全体を統括している。現場を元気にするためには、再生される企業側からものを見て行動することも、もちろん必要だと思う。
星野 小城さんの話を聞いて、あれだけ大きな組織であるカネボウと、小規模な星野リゾート(が関わる案件)の間にも、随分と共通点があるものだなぁと思った。とりわけ、「本気で接しないと、ヒトは斬れない」という話には強く共感した。一方、相違という意味では、リゾート業界というのは、「参加型」「帰属型」で言えば、「参加型」。例えば、調理師は、どこで、どれだけ経験したかというのがステイタスになるので、どんどん変わっていく。そうした組織では、20代、30代の変革を担えそうな、良い人材から順に辞めていくという現実が見られる。うまくいっていないところほど、その傾向は顕著で、しっかり斬るべきものを斬らないと、「星野が来ても、何も変わらないじゃないか」と良い人材が逃げてしまう。(特に参加型組織の場合)ヒトを斬る、というのは、人材流出を防ぐ意味合いも多分にあることを強調したい。
「経営とはヒトを経営すること。その重さと対峙してこそ真のリーダー」(冨山)

■話は少し変わり、「変革のリーダーシップ」の要諦とは。
後藤 目標達成意欲が強いこと。数値目標は常につきまとうので、競走馬みたいなところがないとダメだし、自分自身、頼るのも、そういうヒト。もう1つは、心の強さ。ブレない、諦めない、ということ。先にも言ったように、変革を起こそうとすると、様々な抵抗にあう。「それで本当にいいんですか」と何度も問われる。そういう場面の中には、実は自分自身も自信を持ちきれていないものもあって、でも、それは表に出してはいけない。「まず半年やろう」と、「半年やってダメだったら見直そう」と、ブレたところを見せない心の強さが必要。
星野 3つある。1つは、判断基準がブレないこと。社員が「社長だったらどう考えるか」をイメージできなければいけない。自分の中に確固とした判断基準を持って、共有し、それが、ぶれないことが大切。2つ目は、社員に対する愛情。一番大事なのは社員か顧客かと問われたら、私は社員と答えるし、困ったお客が来たときにも「ぜひ2度と来ないでください」と、社員を守る。周知のとおり、リゾート業界というのは賃金レベルも低いし、皆、贅沢な生活はしていない。物質的なことだけではなく、社員を家族のようにして、いろいろな形で愛情を持って接することが大切と思う。3つ目は、質素倹約。経営者の質素さはリーダーシップになると、私は信じている。どんなに立派なビジョンがあっても、身近さがないと共感はできない。社員と経営者の生活感覚が一致していることが、リーダーシップを発揮する上で、インパクトがあると思う。
小城 リーダーシップの中核は、「ヒトのこころにさわる勇気があるか」(※カネボウの企業理念にこの表現がある)、これに尽きる。
再建に必要なプロセスを考えたとき、戦略立案が実は一番簡単。難しいのは、実行の部分。ヒトに動いてもらわない限り、実行はできない。「お前の言うことなんて聞きたくない」と言われれば、それまで。
ボクは、35歳まで役人、完全なる左脳タイプの嫌なヤツだった。でも、経営者となってからは、ずっと、右脳をどう広げるかということに注力している。ヒトのこころにさわるための、人格、力量をどう広め、どう深めていくか。今度とも努力していかねばならないと考えている。
冨山 この話に関しては、持論というよりは、少し、普遍的な議論をしたい。
まず、「経営には絶対原理がある」ということ。売上-コスト=利益>0という方程式は、企業経営に取り組む限り決して引っくり返すことのできない冷徹な存在であり、経営者はこの現実を直視することから逃げてはいけない。ここから逃げ出した瞬間、粉飾決済のような数字のごまかしに走る。例えば、「なぜカネボウは、あと10年早く繊維から撤退しなかったのか。バカじゃないのか」というような議論がある。しかし、その当時の同社役員会は10人中10人が繊維出身の社員、うち半数は現役の繊維担当役員で構成されていた。売り上げ構成比の5割は繊維で、伊藤淳二氏も元気だった。実際に、そうした状況下におかれて、まともな判断のできる人間がどれだけいるか。おそらく、この会場の誰にも、そうした判断はできないのではないか。それを超えて、やるのが経営者だと、私は思う。
次に忘れてはならないのは、「オペレーションをまわすのが、常にヒトである」ということ。ヒトは、生々しい意思と感情を持った極めて不器用な生物であり、このココロの部分が理解できなければ、経営はできない。
そして何より、「合理と情理のどちらからも目をそむけてはならない」ということ(正反合一、道理)。再生機構で抱える41の案件の全て、キモはここにあると断言できる。ダメな経営者は、ストレスに負けて、どちらかに逃げる。しかし逃げた瞬間、全ては終わる。渋沢栄一氏がかつて「片手に論語、片手に算盤」といったが、それが正鵠を得た言葉と思う。カネの論理(財務)とヒトの論理(事業)の正反合一をとるのが「経営」である。
マネジメントにゴールはない。当たり前の事を当たり前にやり続ける、追求し続けることが、何より難しい(不断のPDCAの繰り返し/個人としても組織としても/環境は変化し続ける)。経営者も自己革新を続けなければいけない。五倫の書の中に「昨日の我に勝て」とあるが、それが嫌になったら、もうダメ。辞め時だ。従って、経営とは常に形を変え続けるべきものであり、「経営とは」という問いかけに対し、命題は言えるが、「これが経営」という話は、辞めてからでなければ語れないことと思う。
マネジメントとは、他者の力を得て何かをやり遂げることだ。しかし、そうは言っても、経営者が「エリート商売」であることは否定できない。これを優越感を持って考えてはならない。その人の決断が、その人以外の人間、ひいてはその家族の人生までも決める、簡単に壊すことのできる重い仕事であることを忘れてはならない。その重みを分かっているのか、責任を背負い続けられるのか。その辛さと対峙し続けるのが経営者の役割だ。
だから、最後の最後は哲学、人格、人間性、世界観の問題となる。星野さんが言われた「質素倹約」もその一つだろう。だから私は、基本的には“子供”が経営するのには反対だ。20代には無理だ。35歳を過ぎてギリギリというところと思う。
敢えていうなら、六本木ヒルズ的錯誤は、そこから来たと思う。村上さんにとって経営はお金のアロケーションであり、それは合理だけでできる。しかし私は、経営とはヒトを経営することと思う。ヒトを経営するとは、ヒトがヒトを裁くということだ。こんな僭越なこと、こんな重いことを子供に理解できようはずもない。
この数年の間に、日本経済はカネの問題はクリアにしてきた。しかし、ヒトの問題はまるで変わっていない。日本企業の現場モラルは極めて高い。再生機構に来た41件の案件のうち、「現場がどうしようもない」というケースは1つもなかった。問題は全て、マネジメントにある。修羅場に自らを置き、鍛錬したという経験を持たない“優等生”ばかりが、はびこっている。彼らが考えるのは、自らの身を守ることだけ。しかし、ヒトの問題を本当に真剣に考えるなら、(先に話したような中間管理層は)自分を削ってでも若い層を採らなければいけない。
経営者とは、最後は、自己鍛錬の経験値の問われる仕事であること。そこを分かり、現実を直視できる人間に将来を担ってもらいたい。だからこそ、この場(あすか会議)にも繰り返し、参加させていただいている。



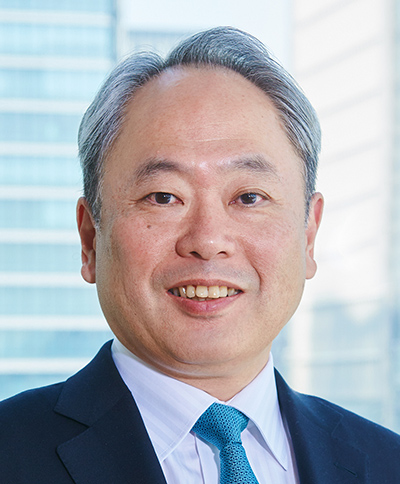





.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)