無事終了したロンドンオリンピック
時差の関係で多くの日本人を寝不足に追いやったロンドン夏季オリンピックが先日終了した。日本選手団は、金メダルの数こそ前回の北京オリンピックより大幅に減らしたものの、金銀銅合わせたメダル数は38個と過去最高を記録した。
男子柔道の不振(史上初の金メダルゼロ)や、宿敵韓国に敗れ44年ぶりのメダル獲得を逃した男子サッカーなど、やや残念に感じる結果もあったが、サッカーは王者スペインに勝っただけでも十分に凄いわけで、概ね多くの日本人は、日本選手団の健闘を評価しているのではないだろうか。
日本人以外でも、ウサイン・ボルトの100M走、200M走、400Mリレーでの圧倒的実力を見せつけた金メダル、最後まで接戦を演じたアメリカドリームチーム対スペインの男子バスケットボール決勝戦、全英ウインブルドンの再現となった男子テニスの決勝戦など、見どころは多かった。筆者個人としては、撮影・再生技術の進化のおかげで、高解像度のスローモーションで演技を再確認することができた男女体操が印象的であった。
開催国のイギリスについていえば、懸念されていたテロがなかったというのが、まずは関係者としてはほっとしたことだろう。過去最高レベルの厳戒態勢を敷いたイギリス政府の面目は保てた格好である。
一方で、空港が大混雑し、期待された観光客による経済効果も思ったほどではなかったというのは、悔いの残るところかもしれない。大会直前にはシティ(ロンドンにある世界的金融街)でLIBOR不正操作疑惑が持ち上がるという間の悪い事件も起こった。開会式では、日本選手団が誘導ミスで退出を促されたり、インド選手団の行進に関係者ではない人間が紛れ込んで問題となるという珍事も発生した。
しかし、世界的有名アーティストが勢ぞろいした閉会式などはやはり圧巻で、かつての世界の覇者イギリスの国力はまずまず誇示できたのではないだろうか。
オリンピックの意義とは何か?
さて、このようにオリンピックは単なるスポーツの大会ではなく、世界中の人々が注目する巨大イベントであり、開催国にとっては国のメンツをかけたデモンストレーションの場にもなっている。企業にとっての絶好のプロモーションの場としての位置づけも大きく増している。
一方で、そうしたナショナリズムの発露や、商業化の拡大に対する批判も根強い。かつてのような「アマチュアの祭典に戻すべき」という声も小さくはない。足掛け3世紀目を迎えた近代オリンピックはこの先どのような姿となるべきなのだろうか?
そのことを議論する前に、まずは近代オリンピックの歴史を振り返るとともに、その活動の基本理念、ルールとなっているオリンピック憲章について見ておこう。
オリンピックの歴史とアマチュアリズム
近代オリンピックは、よく知られているように、フランスのピエール・ド・クーベルタン男爵が、古代ギリシャのオリンピアの祭典にインスピレーションを得て開催を提唱したものであり、1896年にギリシャのアテネで第1回大会が開催された。第1回大会は参加者はすべて男性(女性の参加は第2回大会より)の245名であり、開催期間は1週間、参加国は14カ国にすぎなかった。
途中、2度の大戦による中止や、モスクワ大会(1980年)、ロサンゼルス大会(1984年)の大量ボイコットなどの紆余曲折はあったものの、オリンピックの規模は基本的に拡大基調を描き、今年のロンドンオリンピックでは204の国・地域が参加(ちなみに2012年1月時点で日本が承認している国の数は日本を含め195カ国)、出場者は1万931人に達している。
オリンピックと「おカネ」
その放映権料も最近はうなぎ登りで、国際オリンピック委員会(IOC)によると、2010年のバンクーバー冬季オリンピックと今年のロンドン夏季オリンピックの放映権料は合計約38億ドル、日本円で3000億円に達すると言う。
2006年のトリノ冬季オリンピックと2008年の北京夏季オリンピックの合計が25億ドル程度、「商業五輪のさきがけ」と言われているロサンゼルス夏季オリンピックが3億ドル弱だったことから考えても、その増加ぶりには目を見張るものがある。それだけ世界中で視聴者が増え(現在は220を超える国、地域で放映されている)、かつ関心が高まっていることの証と言えよう。
余談だが、1956年のメルボルン大会は、IOCが放映権料を取ろうとしてテレビ局の反発を買い、オーストラリア以外の放送局はオリンピックを放映しなかったというこぼれ話がある。テレビ黎明期の時代とは言え、現代の感覚からは想像できない事態である。
プロは出場できない?オリンピック選手「アマ」「プロ」の歴史
オリンピックの歴史を語る上で忘れてはならないのは、アマチュアリズムとプロ選手の参加の問題である。
実は、第1回のアテネ大会時には厳格なアマチュア規定は存在しなかったし、クーベルタン男爵自身も後年ほどのアマチュアリズムへの拘りはなかったようである。しかし、徐々に男爵はアマチュアリズムに傾倒し、その徹底が叫ばれるようになっていく。一時は学校の体育教師すら「スポーツでお金を稼いでいる人間」として参加資格がなかったほどである(さすがにこの規定は行きすぎとして早々に廃止された)。アマチュア規定は1914年に起草されたオリンピック憲章にも盛り込まれ、長らくオリンピックの基本精神の1つとなっていた。
アマチュアリズムに拘った最後のIOC会長は、1952年から72年まで会長を務めたアメリカ人、アベリー・ブランデージである。彼は、オリンピックはあくまでアマチュアの祭典であるべきとして、プロ選手の参加を任期終了まで頑なに認めなかった。あるスキー選手が用具メーカーから金銭を得ているとして参加資格を剥奪された事件などが有名だ。
しかし、ブランデージの考え方は、70年代にはすでに「化石」「石頭の郷愁」扱いされていたのが実情である(1887年生まれのブランデージは、1970年代にはすでに80歳代となっていた)。
その大きな理由として、社会主義国家の選手が、実質的にはスポーツで生計を立てているプロ選手であるにもかかわらず、「社会主義ゆえプロは存在しない」という理屈でオリンピックに参加し、好成績を上げていたという事情がある。
西側諸国が本物のアマチュア選手しか派遣できないのに対して、社会主義国が実質プロ選手(これを「ステートアマ」と呼ぶ)を派遣すれば、当然社会主義国側に分がある。このことが不公平をもたらし、西側諸国のメディアやアスリートがオリンピックへの情熱を失ってしまうことが懸念されたのだ。
また、過度にアマチュアリズムに拘ることは、どうしても競技のレベルにキャップをはめてしまうことになる。アスリートとて生活者である。オリンピックレベルで戦うには生活のかなりの部分を練習や試合に割く必要がある。そこで金銭的対価を得てはならないという制約は、かえってオリンピックが本来持つ「より速く、より高く、より強く」という精神に適わないのでは、という声も大きかったのである。
こうした声もあって、ブランデージがIOC会長を退いた1974年、アマチュア規定はオリンピック憲章から削除され、プロ参加の道が開かれた。オリンピックのあり方を変えた大きな変化と言えよう。
商業主義の本格導入はいつから?
オリンピックの歴史におけるもう1つの大きな変化は、商業主義の導入であろう。これは、プロ選手の参加容認と根底でつながる話でもある。
先に、1984年のロサンゼルスオリンピックを「商業五輪のさきがけ」と書いたが、オリンピックのような大きなイベントが商業と無縁で行えるはずもなく、実は早い段階からある程度の商業主義はオリンピックに導入されていた。
先述したメルボルン大会の放映権などもその試みの1つだ。同大会では、アディダスがシューズを選手に無料提供し、新聞や雑誌を通じて世界に伝わることになった。企業が、オリンピックを「効果的なプロモーションの場」と考え始めたのはこの頃のようだ。そしてテレビの普及がこの流れに拍車をかけることになる。
ミュンヘン大会を経て、収入減が多様化
オリンピックロゴの使用権で大会の運営費の一部を賄っていこうという考えが生まれたのは、72年のミュンヘン大会頃からだ。IOC自体がライセンサーとなってライセンス収入を得ようという発想である。
それまでは、入場料収入と宝クジの売上げ、記念切手などからの収入、そして開催国からの補助金(税金)がオリンピックの収入の柱であったが、この頃からテレビ放映料が高騰し、収入源が多様化していく。
転機となったモントリオール大会の大赤字
オリンピックが商業主義に傾いていく決定的なきっかけとなったのは、1976年のモントリオール大会の巨額の赤字であった。筆者個人としては日本女子バレーボールの金メダルと女子体操のナディア・コマネチの大活躍が印象に残っているが、この大会ではおよそ10億ドルの赤字が出たと言われている。およそ3500万ドルという当時としては多額のテレビ放映料収入があったが、それすらスズメの涙と思える赤字額である。支出に全く歯止めがかからず、青天井になってしまったことがその原因とされている(前回のミュンヘン大会で過激派による史上最悪のテロ事件が起き、警備コストが跳ね上がったという事情もある)。
この影響もあって、84年の夏季オリンピック開催に名乗りを上げたのは、78年の開催地決定時点で実質ロサンゼルスだけであった(オリンピックでは、開催の6年前に開催地が決まる)。実は、アメリカは1972年に、1976年開催予定であったコロラド州デンバーでの冬季オリンピックを住民投票で返上したという「前科」がある。84年のロサンゼルス大会についても同様のことが起きる可能性はあったが、IOCもない袖は振れない。ロサンゼルスオリンピックが無事開催されることを半ば願うしかなかった。
なお、80年のモスクワ夏季オリンピックについては、社会主義国家でもあり、またソ連の国威発揚の場という側面もあって国のメンツにかけても成功させるだろうから、財政的な意味での心配は小さかったものと思われる(結果論として、ソ連のアフガニスタン侵攻に対する抗議で西側諸国がボイコットするという想定外の事件はあったのだが)。
支出減・収入増によるロサンゼルスオリンピック成功
84年のロサンゼルス大会はオリンピックの方向性を大きく左右する大会であったと言えよう。すでに88年の夏季大会はソウルで開催されることが決まっていたが、ロサンゼルス大会が財政的に失敗してしまえば、先進国における開催に二の足を踏む国や都市が増えることが予想されていた。収入を増やし、支出を切り詰める――これがロサンゼルス大会組織委員会の至上命題であった。
大会組織委員長を務め、この難しい課題をクリアしたのは、全米でも第2位の旅行代理店を一代で築き上げたやり手のビジネスマン、ピーター・ユベロスである。79年に委員長に選任されたユベロスは会社を売却し、オリンピックに専念する。
支出削減については、極力既存の施設を使い(幸い、ロサンゼルス近辺には、オリンピック使用に耐えうる既存のスポーツ施設が多かった)、また選手村として大学の寮を使うなどのコスト抑制を行った。ボランティアも徹底的に活用した。その結果、モントリオール大会で14億ドル以上もかかった運営費は5億ドル強に抑制された。
同時並行で収入増の施策も打たれた。大きかったのはやはりテレビの放映料で、2億8700万ドルの放映料を得ることに成功した。そのうちアメリカABCが2億2500万ドルを支払った。これは、最低入札価格付きの入札制度を活用した成果である。
もう1つ大きかったのは公式スポンサーを1業種1社に絞り、業界内の競争意識をあおることで、スポンサー料をつり上げたことだ。たとえばコカ・コーラの立場に立つと、ペプシに公式スポンサーの座を取られると、ロサンゼルスオリンピックでのプロモーション活動ができなくなってしまう。
そうした事態を避けたい大手企業は、最低400万ドルに設定されたスポンサー料以上の価格を競って提示してきた。
実は、大赤字となったモントリオール大会からすでに公式スポンサーや公式サプライヤーという制度は導入されており、同大会では600を超える企業が公式スポンサーとなっている。それに対し、ロサンゼルス大会における公式スポンサーはわずか30社強。それにもかかわらず、1億2000万ドルを超える協賛金を得ることに成功した。モントリオール大会の協賛金が数百万ドルにすぎなかったことを考えると、まさに桁外れの収入増であった。
結局この大会は、最終的には2億ドルを超える黒字を計上した。また、放映権に2億ドル以上を投資したABCも最終的には1億ドル以上の利益を上げたとされ、「オリンピックは儲かる」という印象が一気に広まる結果となった。以降、オリンピックはアスリートだけではなくメディアや大企業にとっても一大イベントとなり、現在に至っている。
当初はオリンピック参加に消極的だった一流のプロ選手(特に人気リーグに属するチームスポーツの選手)も、92年のバルセロナ大会のアメリカバスケットボールの初代ドリームチームの出場あたりから、参加に積極的になってきた。残念ながらロンドン大会では正式競技からは外れてしまったが、日本のプロ野球からもレギュラーシーズン中であるにもかかわらず、シドニー、アテネ、北京大会と、多くのスター選手が望んで参加したのは記憶に新しい。
オリンピック憲章の変化
次にオリンピック憲章について見てみよう。オリンピック憲章は、先述したように1914年に起草された(正式制定は1925年)、オリンピックの憲法のような存在である。 現行のもの(2012年8月現在)は2011年に改訂されたものだ。ちなみに、大きな骨格となり細則を支える「オリンピズムの根本原則」と「IOCの使命と役割」は以下のようになっている(上記より引用)。理念の一例としてぜひご覧いただきたい。
オリンピズムの根本原則
- オリンピズムは人生哲学であり、肉体と意志と知性の資質を高めて融合させた、均衡のとれた総体としての人間を目指すものである。スポーツを文化と教育と融合させることで、オリンピズムが求めるものは、努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育的価値、社会的責任、普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造である。
- オリンピズムの目標は、スポーツを人類の調和のとれた発達に役立てることにあり、その目的は、人間の尊厳保持に重きを置く、平和な社会を推進することにある。
- オリンピック・ムーブメントは、オリンピズムの諸価値に依って生きようとする全ての個人や団体による、IOC の最高権威のもとで行われる、計画され組織された普遍的かつ恒久的な活動である。それは五大陸にまたがるものである。またそれは世界中の競技者を一堂に集めて開催される偉大なスポーツの祭典、オリンピック競技大会で頂点に達する。そのシンボルは、互いに交わる五輪である。
- スポーツを行うことは人権の一つである。すべての個人はいかなる種類の差別もなく、オリンピック精神によりスポーツを行う機会を与えられなければならず、それには、友情、連帯そしてフェアプレーの精神に基づく相互理解が求められる。
- スポーツが社会の枠組みの中で行われることを踏まえ、オリンピック・ムーブメントのスポーツ組織は、自律の権利と義務を有する。その自律には、スポーツの規則を設け、それを管理すること、また組織の構成と統治を決定し、いかなる外部の影響も受けることなく選挙を実施する権利、さらに良好な統治原則の適用を保証する責任が含まれる。
- 人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントに属する事とは相容れない。
- オリンピック・ムーブメントに属するためには、オリンピック憲章の遵守及びIOC の承認が必要である。
IOCの使命と役割
-
IOC の使命は、世界中で『オリンピズム』を推進することと、オリンピック・ムーブメントを主導することである。IOC の役割は:
- スポーツにおける倫理の振興、及び優れた統治およびスポーツを通じた青少年の教育を奨励、支援するとともに、スポーツにおいてフェアプレーの精神が隅々まで広まり、暴力が閉め出されるべく努力すること。
- スポーツおよび競技大会の組織、発展、調整を奨励、支援すること。
- オリンピック競技大会が定期的に開催されることを保証すること。
- スポーツを人類に役立て、それにより平和を推進するために、公私の関係団体、当局と協力すること。
- オリンピック・ムーブメントの団結を強め、その独立性を守るとともにスポーツの自立性を保全するために行動すること。
- オリンピック・ムーブメントに影響を及ぼすいかなる形の差別にも反対すること。
- 男女平等の原則を実行するための観点から、あらゆるレベルと組織においてスポーツにおける女性の地位向上を奨励、支援すること。
- スポーツにおけるドーピングに対する闘いを主導すること。
- 選手の健康を守る施策を奨励、支援すること。
- スポーツや選手を、政治的あるいは商業的に悪用することに反対すること。
- 選手の社会的かつ職業的な将来を保証するためのスポーツ組織および公的機関の努力を奨励し、支援すること。
- 「スポーツ・フォア・オール」の発展を奨励、支援すること。
- 環境問題に関心を持ち、啓発・実践を通してその責任を果たすとともに、スポーツ界において、特にオリンピック競技大会開催について持続可能な開発を促進すること。
- オリンピック競技大会のよい遺産を、開催国と開催都市に残すことを推進すること。
- スポーツを文化や教育と融合させる試みを奨励、支援する。
- 国際オリンピック・アカデミー(IOA)の活動、およびオリンピック教育に献身するその他の団体の活動を奨励、支援すること。
このオリンピック憲章だが、21世紀にはいってからだけでも5回変更があるなど、かなりの頻度で変更が加えられている。1つの理由は国の憲法などと違って詳細なルールまで書かれているからであるが、もう1つの理由は、やはり世の中の変化に応じて変えていかないと、オリンピックそのものの存在意義が揺らぐ、という考え方があるからだろう。
歴史を振り返ると、その変更の最も大きなものは、やはりプロ選手の参加を認めたことだろう。一方、上記「IOCの使命と役割」にあるドーピングへの厳しい姿勢や環境への配慮などは、明らかに昨今の社会の要請を反映したものと言える。
ちなみに、かつての憲章ではIOCは開催都市と契約を結び、赤字が出たらその開催都市(実質的には国)がそれを負担することになっていた。しかし、モントリオール大会の大赤字の結果、それではオリンピックそのものが開催できない可能性が出てきた。そこでロサンゼルス大会では市ではなく組織委員会と契約するなど、「苦し紛れの微調整」も実際には行われている。これは、より高次の理念であるである「オリンピック競技大会が定期的に開催されることを保証すること」を重視した結果と言えよう。
ビジネスにおける理念とルール
ここでビジネスにおける理念の話をしておこう。
筆者はかつてこのオンラインマガジンにおいて 「経営理念」という連載を掲載していたことがある。経営理念(philosophy)とは、狭義には、企業が拠って立つ信念や哲学、経営姿勢を表明したもので、「常に新しい価値の創造に挑戦し、ビジネスにおける新機軸を打ち出す」「従業員に対し、相互啓発し成長できる場を提供する」などが典型である。存在意義と言い換えてもいいだろう。
経営理念は、より広義には、企業の大きな方針や方向性を示す、下記のような概念を含むこともある。これらには厳密な定義があるわけではなく、企業によって使い方が違うこともあるが、ここでは最も典型的な使い方を紹介している。「あるべき姿」は、狭義の理念と、ビジョン、ミッションを融合したものと捉えることもできる。
……企業がめざす具体的な目標、像。「二〇二〇年には売上○○円を実現し、△△の分野で世界ナンバーワン企業となっている」など
……企業が責任を持って成し遂げたいと考える任務。使命とも呼ぶ。「社会に対しては●●を、顧客に対しては▲▲を常に提供し続ける」「地球上のすべての国から貧困をなくす」など。狭義の経営理念にかなり近い概念
……従業員に、こういった行動をとってほしいと考える基本的な方向性。「強烈な願望を胸に抱く」「誰にも負けない努力をする」「既存の経営資源に制約されないマインドを持つ」など
……経営理念と行動指針を包含したもの、あるいはこの両者のエッセンスを含みながら両者を接着剤のように結びつけるもの
人事考課のルールやコンプライアンスなどの細かなルールは基本的にこうした理念に基づいて構築されるべき、というのが昨今の経営学の潮流である。より極端にいえば、理念がしっかり明示され、組織に徹底していれば、細かなルールを定めずとも、従業員は自ずと望ましい行動を取るし、その方が細かなルールで縛るより、創造性やスピードも生まれるため、費用対効果が高くなる、という考え方だ。そのためには、理念は魅力的である必要もある。そうでなければモチベーションも求心力も生まれないからだ。
そうした意味で、良い理念の典型として教科書などでよく紹介されるのは、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)の「我が信条(Our Credo)」だ。非常に有名なものであるためご存知の方も多いと思うが、まだ見られたことのない方はぜひご覧いただきたい。
企業において細かなルール決めで大きく揉める場合、実際にはこの理念そのものが問われている、ということも多い。たとえば配当政策について大きく揉めている原因は、単なる財務上の理由からではなく、重要なステークホルダーである株主とどのように付き合っていくのかという理念そのものが曲がり角に来ているから、という場合もあるのだ。そうした場合には、理念そのものに立ち返って、それが時代に合った理念なのか、あるいは様々なステークホルダーにとって魅力的な理念なのかをしっかり見極める必要がある。
理念は、その性質上、ルール(細則)ほど頻繁に変える性質のものではない。しかし、あまりに現場で必要とされるルールとの乖離が大きくなってくるようなら、理念そのものに遡ってそのあり方を考えることも必要なのである。
これからのオリンピックのあるべき姿とは
さて、こうしたことを踏まえた上で、これからのオリンピックはどこに向かうべきか考察してみよう。
現在のオリンピックに向けられている批判の声
以下は、近年よくなされる批判の中から代表的なものをピックアップしたものである。
- オリンピックが儲かりすぎるため、そこに利権が生まれるとともに、行き過ぎた商業主義によって競技の質そのものを損なう事例が生じている
(例:大きな収入源であるアメリカのテレビ局の都合に合わせるため、選手にとっては望ましくない時間帯に競技が行われることがある) - 巨大になりすぎたオリンピックを開催できる国や都市が限定されてきている
- 巨大なスタジアムの建設などが行われるが、それが有効活用されず、開催都市の財政を悪化させている(日本では98年の長野冬季オリンピックが典型)
- 世界的注目度がさらに高まる中、政治的に利用される可能性は相変わらず高い。また、テロの脅威が常に付きまとう
- 開催期間が短いため、ラグビーのような普及したスポーツがオリンピック種目になっていない。ワールドカップという別の目標はあるが、サッカーなどに比べると目標が1つ減ってしまう
すべてを同時に解決する妙薬はなかなかないし、個別かつ地道な対応をせざるを得ないものもある。とはいえ、時間軸も意識して「最大多数の最大幸福」と「公正さ」を同時に追求するなら、上記の1、2、3などは現時点でのオリンピック憲章上も疑問であるから、やはり解決したい課題である。
そこでオリンピックのあるべき姿として、次のような姿はどうだろうか。精緻に分析、シミュレートした上での結論ではないため、やや乱暴な提案もあるだろうが、1つの試案として見ていただきたい。
ただしその場合、各国のオリンピック委員会への分配金が少なくなるため、「適正な利益目標」を設定し、それ以上の儲けは追わないこととする。また、各国のオリンピック委員会への分配金は、その国の競技レベルや経済状況、オリンピック委員会の運営の健全性などに応じてガラス張りで評価し、行う
たとえば、水泳はアジア、陸上はヨーロッパなどと分担することを認めることで1都市あたりの負荷を軽減するとともに、世界中の視聴者の便宜を図る。時期も、たとえばラグビーでは長くとる(すでに開会式前から競技がスタートしていることを考えれば無理な相談ではない)。現実には複数都市での開催にはハードルもあろうが、サッカーワールドカップでは地理的に近いとはいえ日韓共催の例もあり、不可能ではないと考えられる。ただしその場合、現在のオリンピックの高揚感や一体感が失われてしまう可能性や、選手の交流が限定されてしまうというデメリットもある。その部分はIT技術やプロモーションの工夫で補う必要があろう
たとえば64年の東京大会は新幹線や道路などの基本的社会インフラの整備、国立競技場や代々木体育館といったスポーツインフラの整備につながったが、2020年に東京でオリンピックを開催する意義は非常に小さいと思われる。先進国のノウハウや資本は活用しながらも、未来も有効活用できるインフラ整備につながるような途上国の都市を優先する。上記の複数都市分散開催は、小国がインフラ整備を行う上でも有効と考えられる
利権に浸かった委員の強い抵抗はあるだろうが、世論を喚起し、徐々にでも行動を促す
(本来は、理念が浸透していればその必要もないのだが、ここは恣意性を排除する上でも必要であろう)
いかがだろうか?企業変革同様、痛みを伴うステークホルダーも多いため、一朝一夕に進む話ではないと思うが、目指すべき画がないところで議論しても始まらない。叩き台を提示し、議論を促すことが第一歩と考えるなら、様々な人がこうした提案を行うことにはそれなりの意義はあるだろう。
おわりに
世の中にはオリンピック不要論を唱える人間もいるが、筆者は決してそうは思わない。先に紹介した「オリンピズムの根本原則」は、4の一部を除けば概ね賛成であるし、事実、スポーツにはそうした力があると思う。特に、マイナースポーツがオリンピックという「バンドリングされたショー」の場で脚光を浴び、競技人口が増えることは悪いことではないだろう。
問題は何事も「行き過ぎ」である。行き過ぎた国威発揚(典型は1936年の「ヒトラーのベルリン大会」)、行き過ぎた商業主義、行き過ぎた人体改造、行き過ぎた規模…。適切な「あるべき姿」を想定し、理念を振り返ることは、あらゆる組織、活動において必要と言えよう。
読者の皆さんも、ぜひ皆さんなりのオリンピックのあるべき姿や理念を考えていただきたい。同時に、自分の属する組織や活動のあるべき姿や理念が本当にそれでいいのか、ぜひ考える機会を持っていただければと思う。
*本稿の執筆に当たっては、『オリンピックと商業主義』(小川勝・著、集英社新書・刊)のデータを参考にさせていただきました。


.jpg?fm=webp)

































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
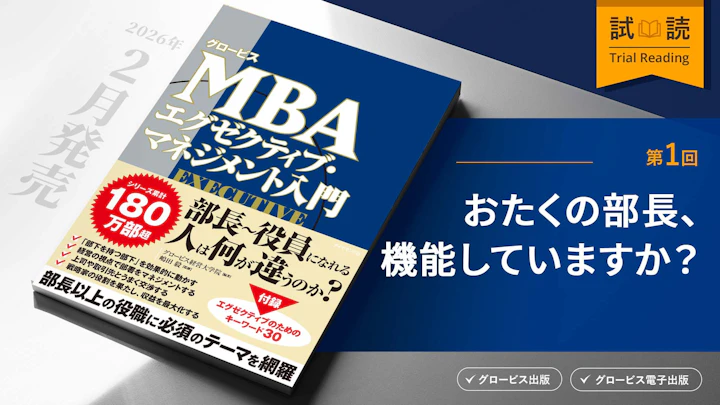
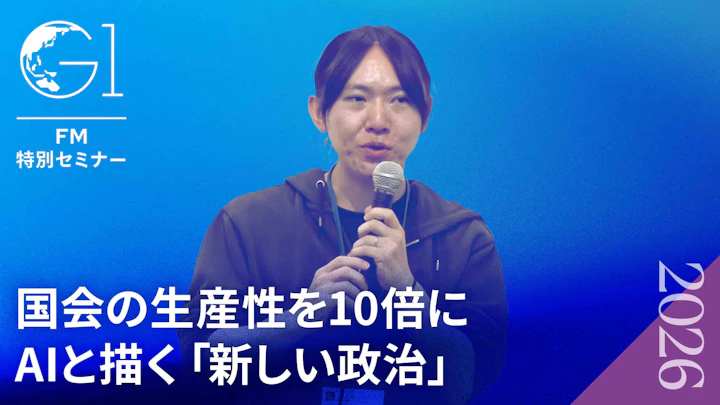


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


