
< 今回のポイント >
◆無料が前提のMOOC、収益化には工夫が必要
◆コンテンツ視点では、修了証を有料で発行、教育機関に販売するなど
◆人材視点では、有能な人材と企業とのマッチング・ビジネスなど
前回はMOOCにおける「修了率」の課題を深く考察しました。
それ以外にもう1つ、MOOCを考える上での大きな論点が「ビジネスモデル」です。つまり、「MOOCでどうやって収益をあげるのか?」ということです。
第6話「教育の可能性が見えてきた!」でも述べたように、MOOCの可能性の1つは「民主化」であり、「教育機会格差の解消」、つまり教育の裾野を広げることにあります。したがって、MOOCの基本的な発想の原点は「無料」です。
では、無料であることを前提に実際にどうやったら収益化できるのでしょうか?
特にUdacityとCourseraは、edXと違ってそれぞれベンチャーキャピタルから多額な資金を提供してもらっている営利団体であるためにこの「収益化」は大きな課題でもあります(edXはMITとハーバードが資金拠出をした非営利団体です)。
その戦略を考えていくためには、MOOCが抱えるアセットである「コンテンツ」と「人材」に注目する必要があります。その2つの側面についてそれぞれ具体的に見ていきましょう。
1. コンテンツをベースに収益化する
(1) 修了証/学位による収益化
素直に考えれば出てくるモデルの1つが「修了証発行」というビジネスチャンスです。つまり、「学ぶのはタダ、でも修了証まで欲しければお金がかかる」というものです。
実際にこの仕組みを入れているところは数多くあり、たとえば実際にCourseraのサイトを覗いてみると、正規の修了証が獲得できるものは現時点で200を超えるコースが存在します。学ぶのは無料ですが、インストラクターからの修了証を取得するためには49ドル(6000円程度)がかかります。ただし、これは単なる修了証であり、単位にはなりません。あくまでも、「Courseraでの課程をちゃんと修了したことを認めます」というものです。
他方、Udacityはナノディグリー(Nanodegree)というオリジナル(非認定)の学位を発行するプログラムを開発しました。

AT&Tやグーグルと共同し、モバイルやWebコンピューティングの技術向上を目的としたプログラムであり、テクノロジー領域での就職を志す人をターゲットにしています。現状「データアナリスト」や「iOS開発者」など5つの学位プログラムが存在しており、1カ月200ドルで、半年から1年程度で修了することができます。修了までに合計2000ドル程度かかるとはいえ、通常この手の専門学校は1万ドル以上かかる場合が多いことを考慮すれば、シリコンバレーでの就職を真剣に考えている人にとっては魅力的なサービスかもしれません。
このナノディグリーは、映像視聴を中心とした既存のMOOCモデルとは異なり、プロジェクトベースで実際にアウトプットを出しながら進めるとともに、そのプロジェクトに対してコーチからの直接的なフィードバックが入るなどのサポートもあります。これらのサービスは第7話で課題点としてあげた低い修了率に悩んでいたセバスチャン・スラン氏にとっての解決策となりました。
あるインタビューでスラン氏は、「学生が受講料を払うと修了率は70%と飛躍的に高まる」と胸を張って答えています。Udacityにとって、これは「修了率向上」と「収益化」を実現する一石二鳥のサービスと言えるのかもしれません。
しかし、このナノディグリーがCourseraやその他のサービスと違うところは、「入口からしてそもそも無料ではない」ということです。したがって、このサービスをMOOCと呼んでいいのか、という点は議論があるかもしれません。スラン氏当人としては、MOOCの定義なんてどうだっていいのでしょうが…。
(2) 教育機関への販売を通じた収益化
もう1つの方向性は、一連のMOOCコンテンツを大学などの教育機関にパッケージでライセンス販売し、大学はそのMOOCコンテンツをベースにクラスを組み立てるようにする、というものです。いわゆるB2Bビジネスで、ビジネスとしてみれば、「教科書販売」というモデルに近いのかもしれません。
まず予習としてMOOCのコンテンツを見ておき、必要な知識部分は予めそこで吸収し、疑問を解消しておきます。その上で、集合したクラスルームにおいては、その知識を前提にした議論を行う、というものです。
MOOCの良さを活かしつつ、その弱点を集合の場で補う、というもので、これは一般的に「反転授業」と言われる授業スタイルです。
MOOC提供側にとって収益源の多様化につながるとともに、購入側の教育機関としても、「ハーバードやMITなどの著名校のコンテンツで学ぶことができる学校」とアピールすることができる、という観点において、双方にとって意味があるサービスになります。
実際に、たとえばedXは、バンカーヒル・コミュニティ・カレッジやマサチューセッツ・ベイ・コミュニティ・カレッジという教育機関に対してMITのコンテンツをライセンス提供する、ということを始めています。
このMOOCを通じた「反転授業」の推進は、今後も一般的な教育機関のみならず、法人研修の場も含めてさらに進んでいくことが予想されます。
我々グロービスの法人研修部門もMOOCで作ったコンテンツを事前視聴にして、リアルのクラスで徹底的に議論する、という「反転化」の動きを進めていますが、そういったことも含めてB2Bには極めて高い可能性が残されているでしょう。
2. 人材をベースに収益化する
今までコンテンツという資産をベースにしたビジネスを考えてきましたが、他方で忘れてはならないのが、MOOCが持つ「人材」というアセットです。MOOCは国境を超えて多くの埋もれた人材を引き寄せる「磁力」があります。第6話でも伝えましたが、そのような人材を集めるだけでなく、その能力を可視化できる、ということにMOOCビジネスの大きなポテンシャルがあります。
たとえばedXにおけるアガワル学長の「電子回路」のクラスでは、わずか0.2%しかいなかった満点取得者の中に、ウランバートルの15歳の高校生がいる、ということが分かりました。オンラインがなければ埋もれていたかもしれない才能を発掘できる、ということはMOOCの1つの大きな武器です。結果的にこの学生は、MOOCをきっかけにMITを受験し、無事入学したようです。
この「人材発掘」という側面に着目した収益化の具体的な動きはいくつも起きています。
UdacityはGoogleやFacebookなどの企業と提携したプログラムを開発し、そのプログラムを通じた人材育成を行う一方で企業と個人をマッチングさせる仕組みを導入しています。MOOCの持つ磁力を武器に、このプラットフォームを通じて企業と個人をマッチングさせ、そのマッチングを通じて収益を得る、という構図です。
特にテクノロジー系のスタートアップ企業にとって、高度なスキルを持った優秀な人材は喉から手が出るほど欲しいものです。それを今までは限られた人材マーケットの中で奪い合いをしていたわけですが、MOOCは国境を超え、能力を視覚化することによってその人材マーケットサイズを一気に広げる役割を果たそうとしています。
もちろん、受講者側としても、しっかり勉強をして良い成績を収めることができれば、世界のどこにいようとGoogleのような企業の目に止まることができる、ということは魅力的であることは間違いないでしょう。
さらに、Udacityはジョージア工科大学、そしてAT&Tと手を組んで、修士発行プログラムを実施することにしました。学生は授業料として6600ドル(80万円程度)を支払うことで、ジョージア工科大学のプログラムがUdacity上で(=オンライン上で)学ぶことができます。そして一定の条件を満たせば修士(Online Master of Science : OMS)という学位が授与されます。このプログラムに対して200万ドルという資金を拠出しているのがAT&Tです。AT&Tはそのリターンとして、優秀な人材をリクルーティングすることができるようになるのです。
以上、MOOCのビジネスモデルを「コンテンツ」と「人材」という側面から探ってきました。
これらの動きをみればお分かりの通り、今やMOOCと言われたサービスプラットフォームも、必ずしも「Open: 無料公開型」や「Massive: 大量受講型」にこだわっているわけではありません。修了率や収益化などの様々な課題に直面しながら、当初の定義の範疇を超えつつあるのです。
もはやMOOCとそれ以外のオンライン教育サービスの垣根はなくなりつつあるのが実態であり、「MOOC」という呼び名が過去のものになるのも時間の問題かもしれません。
次回は、この流れを踏まえて、MOOC以外のオンライン教育全般の展開を見ていきたいと思います。
【関連情報】
>> 自宅や出張先でもOK!通学せず効率的にMBAを学ぶ




























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)













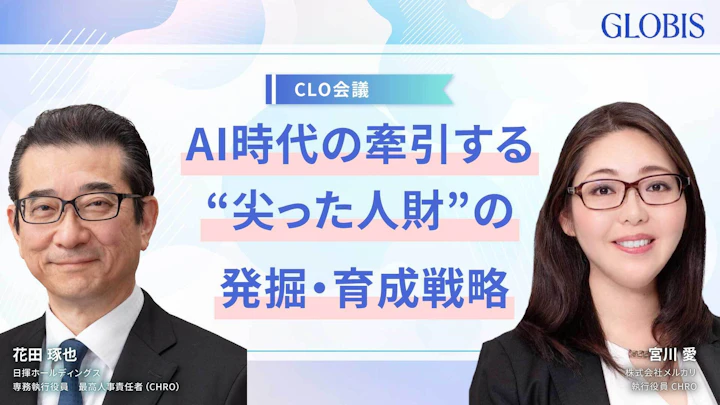

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
