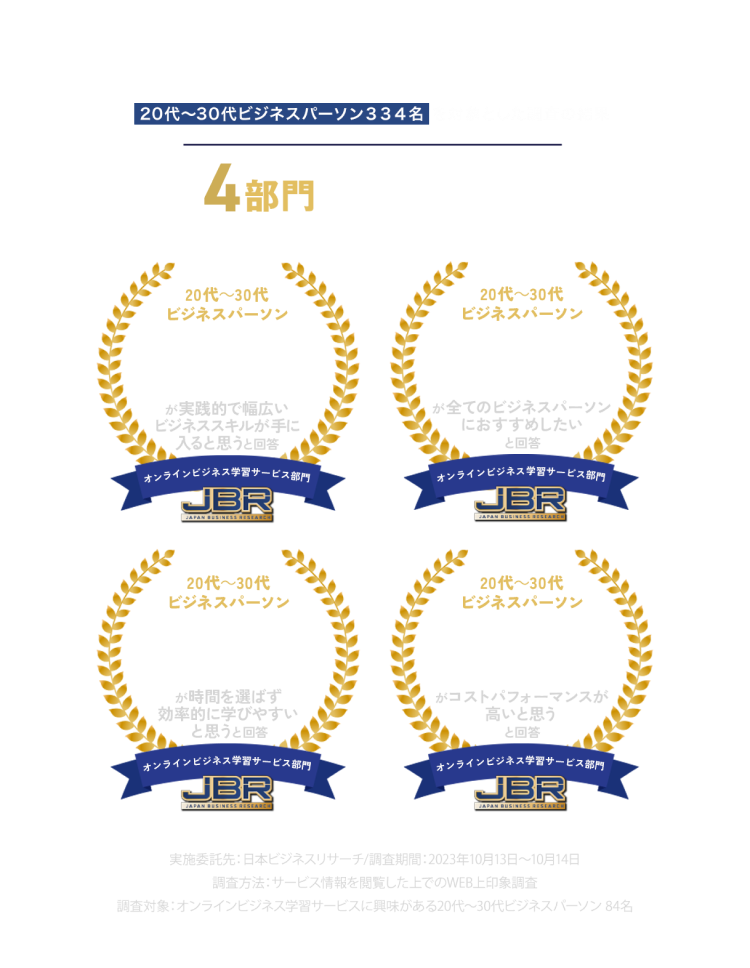フランスワインの二大銘醸地のひとつであるブルゴーニュにワインがどのように根付いていったかを検討した前回に続き、今回は、もうひとつの銘醸地であるボルドーに目を向け、綴っていきたいと思います。
フランスという国は、六角形で表すと分かりやすいとよく言われます(右の図を参照)。六角形は、6つの三角形の頂点が中心になるように集合させると作ることができますが、六角形の1つの頂点を真北において、西半分に3つの三角形、東半分に残りの3つの三角形をおきます。そうすると、反時計回りに、左上の三角形1番はドーバー海峡を挟んでイギリスに対峙するノルマンディ地方、真左の三角形2番は大西洋を正面にたたえるアキテーヌ地方、左下の3番はピレネー山脈に面するスペインとの国境地帯、右下4番は地中海沿岸に臨むナルボンヌからマルセイユをカバーするラングドック地方とプロバンス地方、真右5番はスイス、ドイツ南部の国境と接するアルプス山脈からアルザス地方一帯、そして最後の右上6番の三角形がドイツ西部、ルクセンブルグとベルギー国境と接するロレーヌ地方からシャンパーニュ地方一帯という具合です。
これらの6つの六角形の中で、3番から5番までは、概ね標高が200メートル以上の高台や山岳地帯で、残りの三角形は標高20メートル未満の平野部です。この平野部はさらに二つに分けることができ、一つ目が大西洋に臨む三角形2番のフランス西部の領域、二つ目が三角形の1番と6番のイギリスに面する地方からベルギーとルクセンブルグに接する地方をカバーしたフランス北部一帯です。
この中で、フランスワインの二大銘醸地のひとつであるボルドーは、三角形の2番、平野部でいくと大西洋に臨む一帯のやや内陸にある商業都市です。そして、このボルドーが属する一帯の地方をアキテーヌ地方と呼びますが、これは紀元前56年にローマ帝国に征服され属州となった際に、アクイタニア(水の国)と呼ばれたことに由来しています。また、ボルドーはフランス語表記で「Bordeaux」、この単語を分解すると「Bord-eaux」となり、「Bord」は「縁」、「岸」、「eaux」は「水」という意味ですので、そこからも、この地域一帯が水とは切っても切り離すことができないことが想像できます。
「ワインの女王」と呼ばれるボルドーワイン
ボルドーは川岸にある街で、大西洋に注ぐジロンド河を約80キロメートル遡り、そこでドルドーニュ河とガロンヌ河に二股に別れたところで、右方向から注いでくるガロンヌ河をさらに約20キロ遡ったところにあります。この街は、外海からの商船のアクセスが良かったため、商業港として発達してきました。今回の内容より時代は先となりますが、エドゥアール・マネの「ボルドーの港」という1871年に描かれた作品には、数多くの船が川べりにひしめきあっている様子が描かれており、その様子が伺いしれます。
しかし、地の利があるこのアキテーヌ地方は、それゆえに、領土争奪戦の格好の場所でもありました。紀元56年にローマ帝国に征服された後も、匈奴(きょうど)と思われるアジアの遊牧民フン族がヨーロッパに西進したことをきっかけにおきたゲルマン民族の大移動で、アキテーヌ地方にはゴート族、ヴァンダル族、西ゴート族などが、次々と侵入してきました。476年にローマ帝国が滅亡した後は、507年に今のフランスであるフランク王クロービスが西ゴート王国のアラリック2世を打ち破り、アキテーヌ地方はフランスに統合されますが、クロービスの死後、今度はスペインのバスク人の侵入を受けます。その後、カール大帝が778年にスペイン人を打ち破り、再びアキテーヌ地方を統合しますが、今度はヴァイキングの侵入を受けます。
このようにアキテーヌ地方は、侵入を受けやすい場所であり、紛争が絶えない場所でした。そして、支配者が次々と変わっていく土地柄のため、イスラム文化の影響を受けたり、北フランスほど徹底した家父長制度、封建制度、領主制度などが発達しなかったりと、独自の文化が発達することになり、紛争の中でもローマ帝国時代の都市生活は存続し、ボルドーはこの地方の政治・宗教・商業の中心地であり続けました。
最終的には、1137年にアキテーヌ公国ギョーム10世の娘エリオノールがフランス王子ルイ(同年ルイ7世として即位)と結婚し、ボルドーはフランスに統合されます。しかし、1152年、ルイ7世とエリオノールは離婚。その同じ年に、エリオノールはイギリス・プランタジネット家のアンリと再婚し、1154年にはアンリがイングランド王ヘンリー2世となります。ここで問題になるのが、アキテーヌ地方が常にエリオノールと一緒について回ったことです。つまり、ルイ7世と結婚したときに、アキテーヌ地方はフランスに統合されますが、その後ヘンリー2世と再婚したときには、アキテーヌ地方が今度はイギリスに統合されるということになったのです。
以来1453年まで約200年間、ボルドーとイギリスの長い関係が続きます。この200年間は、三角形の1番と2番をイギリスとフランスで獲り合う長い戦争の時代でした。12世紀ころのイギリスとフランスの領土は、大まかにイギリスが三角形の1番と2番、フランスは3番から6番という関係であったようですが、その後、イギリス領は圧迫され、15世紀のころには三角形の2番の南部まで押し込まれていました。
以上、ボルドーの歴史的背景を振り返ってきましたが、このようなイギリスとの密接な歴史が現在でもボルドーワインが『ワインの女王』と呼ばれる所以であるわけです(なお、ブルゴーニュワインは、『ワインの王様』と呼ばれています)。
そして、13世紀に入ってボルドーが重要なワイン産地として認知され始めます。第5回のコラムでボルドーの厳しい気候に耐えられる「ビトゥリカ」という品種がもたらされたお話を記しましたが、このお話はおよそ紀元1〜2世紀ほどのことでした。それからボルドーがワイン産地として陽の目を見るまで1000年以上もの時間を必要としたのでした。
さて、この1000年の時間の流れに終止符を打ち、ボルドーがワイン産地として発展していくのは何がきっかけだったのでしょうか?
中世のワイン生産地と消費者
13世紀中ごろに、イタリア人修道士サリムベーネはワインを大量に生産する土地として、ラ・ロシェル、ボーヌ、オーセールの3カ所を挙げているようです。ラ・ロシェルはジロンド河の河口から50キロほど北にある海に面した街です。ボーヌは、ブルゴーニュ地方の中心地、そしてオーセールは、ボーヌとパリを結んだ間くらいにある地域です。先ほどの三角形でいうと、ラ・ロシェルは真左の2番、ボーヌとオーセールは右上の6番に含まれます。
さて、もうお気づきと思いますが、このイタリア人修道士の記述の中に、ボルドーのワインというのは挙げられていません。ボルドーは当時、フランスにおいてまだ主要産地ではなかったのです。また、ボルドーは三角形2番に位置し、ラ・ロシェルと同じ場所であるため、当然、競争が発生することも想像されます。
そうです、ラ・ロシェル、ボーヌ、オーセールの三大生産地に対して、二大消費者が、フランス国王と、イギリス国王でした。そして、三大生産地のうち、ラ・ロシェルを追撃しようとするボルドー、こういった構図が当時のワイン市場で起きていたと考えられます。
この構図をベースに、それぞれの生産地から見て、どの顧客を狙うかを考えると、選択肢はおのずと決まってしまいます。ボーヌとオーセールはパリにいるフランス国王が地理的に最も有利です。パリを素通りしてイギリスにアクセスするのは、よっぽど在庫があまっていない限り、優先度は下がります。一方で、ラ・ロシェルは、大西洋沿岸に位置する街のためフランス国王とイギリス国王の両方にワインの供給が可能です。
ラ・ロシェルという街は、もともとその沿岸沖にある、レ島とオレロン島で海水を蒸発させて生産される塩で利益を得てきました。12世紀ごろ、ギョーム10世は、この利益をベースにラ・ロシェルに港を建設し、「新しい素敵な街」として益々栄えることになります。特に、船舶技術の発達とともに彼らが現金取引をおこなったことで、富裕層の集まる町になっていました。
船舶技術とは、コーグ船と呼ばれ、それまでの甲板の船とは大きく異なり、両舷の丸い大型船で、積載量が格段に大きくなりました。1225年にはイギリス・ヘンリー国王が220トノー(現在のワインボトル26万8000本相当)におよぶワインを大型船で運んだという記録もあります。このような大規模な取引で富を増やしていったラ・ロシェルの商人たちは、1262年マルグリット・ド・フランドル伯夫人からさまざまな免税特権や商取引上の便宜を与えた特許状を得ることになります。
このような状況下、ボルドーは、パリやイギリスからみてラ・ロシェルよりもさらに南の遠方にあるため、中世のワイン市場の構図の中では不利な場所に位置していました。これに追い討ちをかけるように、ラ・ロシェルには免税特権や有利な商取引を許可した特許状があったというわけです。
ボルドーの興隆
ボルドーの興隆のカギは、やはりラ・ロシェルという“目の上のたんこぶ”を無力化することでした。そのために、ラ・ロシェルと直接戦うというのではなく、ラ・ロシェルの重要顧客であるイギリス王に取り入る機会をボルドーの商人たちは、虎視眈々とうかがっていました。
そして、その機会が訪れます。一つ目が、1205年から1206年のイギリスと現在のスペインにいたカスティリヤ王アルフォンソ8世との戦争、もう一つが1224年の同じくイギリスとフランス王ルイ8世との戦争です。
1205年の戦争では、ボルドーの人たちはカスティリヤ王のアキテーヌ南部ギュイエンヌと徹底的に抗戦し、その侵入を喰い止めました。その結果、イギリス王の感謝を引き出すことに成功します。そして、ボルドーの人たちが、イギリス王のために土地を守った報酬として、イギリス国王はボルドーからワインを調達するようになりました。もともと、質の高いワインですから、一度イギリス国王御用達になるとボルドーワインの販売は一気に拡大しました。1206年以降、イギリス王家の食卓や国王の贈答用ワインの一覧表に頻繁にボルドー商人から買い付けたワインが登場するようになります。1215年にはジョン王はボルドー商人から120トノー(108キロリットル=現在のワインボトル14万4000本相当)ものワインを買い付けた記録があります。
そして、決定打となるのが1224年のイギリスとフランスの戦争です。戦争が勃発して間もないころボルドー市長とボルドー市は、イギリス王国の大法官であるヒューバート・デ・バーグに書簡を送付しました。
「閣下、二オールの城とサン・ジャン・ダンジェリーの町は降伏したわけでもないのに、フランス王に降伏したことをお伝えいたします。この書簡を運ぶ者が私たちのもとを去る時点で、フランス王はラ・ロシェルの城壁に迫っていました。わたしどもといえば、イギリス王の敵と戦い、あくまでも忠誠を誓う所存でおります。あらゆる手だてを尽くして、ボルドー市の守りを固めておりますが、そのために何軒もの家を取り壊さねばなりませんでした。このことによってわたくしどもがどれほどの損害を蒙ったか、申し述べることができないほどです。・・・これらの出費や損失も、すべて公共の利益に不可欠との思いで遂行しております。わたくしどもが忠実なしもべとして命の続くかぎり仕えるわれらが主君であるイギリス王が支配する町、ボルドーを守らなくてはなりません」*1
ラ・ロシェルにしてみれば、上客としてイギリス王とフランス王の両方を押さえている中で、イギリス王がボルドーに好意を寄せていく様子をみると、イギリス王から心が徐々に離れていったことは何となく想像できなくはありません。また、ラ・ロシェルとしては、イギリス以外にも北の海やバルト海まで交易していましたので、イギリスはどうしても押さえなければならない顧客というわけでもなかったとも言えるかもしれません。一方で、それまで中心的なワイン産地として注目されていなかったボルドーは、イギリス国王という上客を重点攻略したということです。こうした、ラ・ロシェルとボルドーの人たちの心の機微が、英仏の戦争をきっかけに大きな動きとなり、ついにボルドーが主要なワイン産地として名乗りをあげるのです。
その後、ボルドーはイギリス王から次々と特権を得ます。たとえば、14世紀には「ワイン取締法」によって、たとえば次のような特権が与えられました。
・ボルドーのブルジョワたちのブドウ畑が集中する近郊地域のワインの独占販売権をボルドーのブルジョワたちだけに与えること
・ブルジョワの所有する畑以外のものをボルドー市内で販売するには、すべてのブルジョワたちが自分たちの販売用ワインを売りさばくのを待たなければならないこと
・「ボルドー市民」と呼ばれる人々が、外国の仲買人たちにとって唯一の売り手であること
・サン・マケール(ボルドーよりガロンヌ河を上流に遡った街)より上流の地域は、クリスマス以降でなければ、ボルドーにワインを運んではならないこと
いずれも、ボルドーワインを優遇するもので、こうした“ボルドー特権”は、17世紀ごろまで続くのでした。
このように、ボルドーワインの発展は、ブルゴーニュ地方とは打って変わって、商人たちが国王からいかに特権を勝ち取るかの利権の争いに勝利したことがきっかけでした。この違いは、ブルゴーニュ地方のブドウ栽培が、細かく畑ごとに分類されている一方で、ボルドー地方のブドウ栽培は、シャトーごとに分類されている遠因と思われます。シャトーは文字通り「お城」ですから、貴族がワイナリーを経営したことが伺われますが、国王から特権を得るような人たちは貴族であったということではないでしょうか。
いずれにせよ、このような異なる経緯を経て、フランスワインの二大役者が出揃ったのでした。そして、さらに時代は進んでいきます。それまで、ワインが高価で、主な顧客といえば国王といった人たちでしたが、ワインが大衆化されていくのです。次回のコラムでは、このフランスにおけるワインの大衆化が、ワインビジネスの視点でどう起きたのかを綴りたいと思います。
*1ロジェ・ディオン、『フランスワイン文化史全書ブドウ畑とワインの歴史』、国書刊行会
*参考文献
ロジェ・ディオン、『フランスワイン文化史全書ブドウ畑とワインの歴史』、国書刊行会
ヒュー・ジョンション、『ワイン物語上』、平凡社
『世界大百科事典』、平凡社
『図解世界史』、成美堂出版
宮崎正勝、『早わかり世界史』、日本実業出版
MicrosoftEncarta
▼「ワイン片手に経営論」とは
現在、ワイン業界で起きている歴史的な大変化の本質的議論を通して、マネジメントへの学びを得ることを目指す連載コラム。三つの“カクシン”が学びのテーマ。一つ目は、現象の「核心」を直感的に捉えること。二つ目は、その現象をさまざまな角度から検証して「確信」すること。そして、三つ目は、その現象がどう「革新」につながっていくのかを理解すること。
【お知らせ】本欄の著者・前田琢磨氏の翻訳書『経営と技術—テクノロジーを活かす経営が企業の明暗を分ける』(クリス・フロイド著、英治出版刊)が発売になりました。さまざまなベストプラクティスを取り上げながら、技術マネジメントの在り方について議論した一冊です。