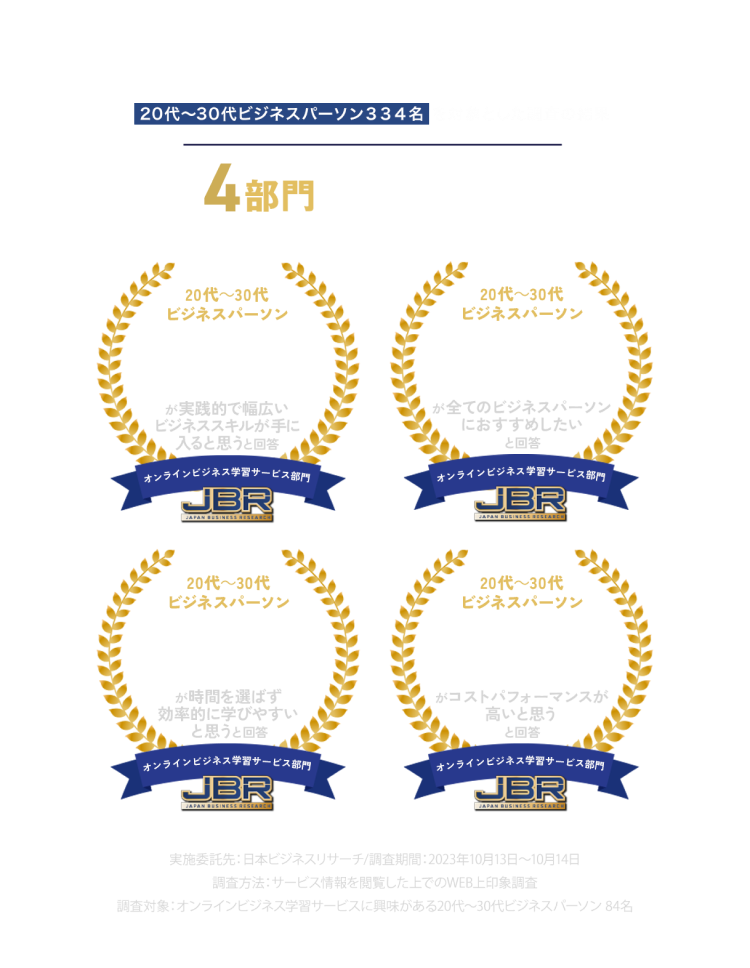噴き出すナショナリズム

この夏の政治・国際ニュースとして、竹島をめぐる韓国との軋轢、そして尖閣諸島をめぐる中国、台湾の激しい行動について触れないわけにはいかないだろう。
特に尖閣諸島をめぐる中国の行動は、ここ数年なかったような緊張を日中間に生み出した。各地で反日デモが起き、日系の店舗・オフィスや、日本人を相手にした店舗が、デモの標的とされた。中にはデモとは名ばかりの略奪などもあったようで、現地のイオンなどは大きな損害を被ったとされる。また、現地のスタッフの独断(本稿執筆時点の報道による)で尖閣に言及する張り紙をウインドウガラスに張ったユニクロは、日本の愛国的な人々から怒りを買い、またビジネスモデルが中国での生産を前提としていることから、1日で株価を7%以上下げるという事態にも見舞われた。
一説には、今回のデモは中国指導部の交代に絡み、各派閥の思惑が複雑に交差したためにおきた「複合官制デモ」との分析もあるようだが、いずれにせよ、複雑な国内事情(所得格差の拡大、共産党への不満など)を抱える中国が、国民の対内的な不満のはけ口として今回のデモをある程度黙認し、同時にそれによって政府共産党の求心力を増そうとしたという分析は一定の説得力を持つ。
実利的・経済的な観点からみれば、日中両国のビジネス関係が悪化してしまうと、長期的に見て両者に得はないはずである。しかし、そう簡単に割り切って話が進まないのが国家や国民というものである。感情を持つ人間という動物が関与する営みである限り、強い感情が合理的な判断を妨げてしまうという認識は常に持つ必要があろう。
さて、ビジネス同様もしくはそれ以上にナショナリズムという強い感情に翻弄されてきたのがスポーツである。本稿では、スポーツがナショナリズム高揚の手段としてどのように用いられてきたか、その典型例をみるとともに、それと良い関係を築く上でのヒントについて考察してみたい。
なお、ナショナリズムは単なる愛国心という意味以上に複雑な意味合いを帯びる用語であり、状況によっては国粋主義や民族主義と訳されることも多い。ここでは、それらを包含した思想・運動と、やや広義の意味で用いていく。
最悪の見本――1936年のヒトラーの「ナチ・オリンピック」
前回のオリンピックに関する考察でも少し触れたように、スポーツイベントとしてのオリンピックは、その規模、参加国数、4年に1度という希少性、競技レベルの高さ、必要となるインフラ(その国の経済力や国力を示す)、そしてそれらゆえに生じる注目度の高さから、群を抜いて人々のマインドに影響を与えうるイベントと言える。それに次ぐのが男子サッカーのワールドカップだろうが、おそらくオリンピックは、その数倍のインパクトを持つものと想像される。
ただですら目立つ大会であることに加え、オリンピックでは「国」というものが極めて強調される。どんな国際大会でも、どの国の選手かということは当然重要視されるが、オリンピックのそれはまさに桁違いだ。しかもオリンピックには伝統的に、「国」を意識させる行事やシーンが多い。国ごとに入場する開会式や、各競技の表彰式の国旗掲揚、国歌の演奏など。最近では、競技終了後に国旗を持ってウイニングランをするというシーンも一般的となった。常日頃、国旗や国歌にニヒルな態度をとる日本人ですら、日本人選手のメダル獲得後に日の丸がポールに上がり君が代が流れると何とも言えない高揚感を感じるという人は少なくないはずだ。
そうしたオリンピックの場を国威発揚の機会をとして最も効果的に(しかし最悪の形で)利用したとされるのが、1936年にベルリンで開催された別名「ナチ・オリンピック」である。
1933年に政権の座に就いたアドルフ・ヒトラーは、すでにベルリンでの開催が決まっていたオリンピックを徹底的に国威発揚、さらには(ユダヤ民族に対する)アーリア民族優勢を示す場にしようと決意する。「プロパガンダの天才」とも言われた国民啓蒙・宣伝大臣のヨーゼフ・ゲッペルスが自ら演出の指揮を取り、ヒトラーの開会宣言中には10万人を超える観客がナチ式の敬礼をするなど、大会は異様な興奮の中で幕を切る。結局この大会では、ドイツは金銀銅あわせて89のメダルを獲得し、2位アメリカの56個を抑えて圧倒的なトップを獲得する。その前の1932年ロサンゼルス大会のメダル獲得数が20個で5位(1位のアメリカは103個。金メダルに限れば、ドイツは3個で9位)だったことを考えれば、劇的な躍進と言えよう。
この大会の模様は記録映画『民族の祭典』『美の祭典』として映像化もされ、ドイツを始め世界中で多くの観客を獲得した。まさにナチのプロパガンダは大成功を収めたのである(両作品の監督は、ナチを賛美した記録映画『意志の勝利』のレニ・リーフェンシュタール)。
オリンピックの成功に自信を得たドイツは、さらに国力を高め英米仏といった列強先進国に追いつくべく、軍事力を増強し、版図拡大を目指して突き進んでいく。その後の歴史は皆さんご存じのとおりである。
ちなみに、このベルリン大会は日中戦争前夜の日本にとっても重要な大会であった。当時は開催5年前にオリンピックの開催地が決まることになっていたが、次の1940年の開催地決定は、諸事情あってまさにベルリン大会の前夜にまで持ち越されていたのだ。そして、そこで有色人種の国としては初めて東京が開催地として決定される(その陰には、当時の友国イタリアの辞退という事情もあった)。人々はこのニュースに熱狂し、その熱狂の中で、人々は普及が進みつつあったラジオでベルリンオリンピックの中継やニュースに耳を傾けたのだ。河西三省アナウンサーの「前畑がんばれ」という放送史上に残る実況は、この大会時のものである。その後の大戦につながる「死に物狂いでやれば白人にも負けない」という意識は、こうしたスポーツ大会を通じても植え付けられていったのである。
オリンピックに対する政治の関与
その後も、ドイツのナチほどではないにせよ、オリンピックはまさにオリンピックであるがゆえに、さまざまな政治的思惑に翻弄されてきた。戦後の代表的なものを上げると以下のようなものがある(ここでは夏季オリンピックに限定して事例を紹介する)。
・1952年ヘルシンキ大会からソ連がオリンピックの場に帰ってきた。この時期は東西冷戦が厳しい頃で、以降40年弱にわたって、オリンピックは東西両陣営のメンツの張り合いの場ともなった。東側陣営の、ステートアマと呼ばれる「実質はプロでありながらアマチュア扱いされた選手」の台頭により、オリンピックの精神が一時期かなりゆがめられるようになったのは、前回のコラム紹介したとおりである。また、東側諸国が国家的なドーピングを行っていたという噂は今でも根強い。円盤投げなどは、男女とも80年代の東ドイツ選手の記録が今でも世界記録であり、そうした疑惑の根拠とされることが多い。また、70年代までは、「2つの中国」をめぐって、中華人民共和国と台湾の参加をどう扱うかが国際オリンピック委員会(IOC)の悩みのタネであった。
・1968年のメキシコ大会は、当時アメリカで公民権運動が盛んだったこともあり、人種差別が大きな話題となった大会であった。大会直前には、IOCが、アパルトヘイトを実施していた南アフリカの参加を認めたことから、アフリカ26カ国が出場ボイコットを発表するという事態になった。これに共産諸国も追随したことから、一時は50国以上がボイコットを表明する。結局、IOCが南アフリカの参加を却下したことで、ボイコットは回避されたが、オリンピックのあり方を大きく揺さぶる事件となった。大会期間中には、男子陸上の2選手が表彰台上でブラックパワーを象徴するブラックパワー・サリュートを行ったことで、IOCから永久追放処分を受けるという出来事もあった。
・1972年のミュンヘン大会は、パレスチナ武装組織「黒い九月」が選手村に乱入して人質事件を起こし、結果として、イスラエル選手や関係者11名が殺害された。これはいまだにオリンピック史上最悪のテロ事件である。翌1976年のモントリオール大会では、アフリカ20数カ国が、ニュージーランドのラグビーチームが南アフリカに遠征したことに対するペナルティを受けなかったことに抗議してボイコットした。
・東西冷戦の最後の鞘当て合戦が1980年のモスクワ大会と、1984年のロサンゼルス大会の、両陣営の大量ボイコットである。中には、モスクワ大会に参加したイギリスや、ロサンゼルス大会に出場したルーマニアのような国もあったが、多くは米ソの顔色を気にして、彼らに従った。日本も、80年のモスクワ大会はボイコットしている。現場に近い日本オリンピック委員会(JOC)は最後まで抵抗したようだが、政府から補助金打ち切りをチラつかされてはボイコット以外の選択肢はなかった。
驚くのは、84年のロサンゼルス大会で、大国とは言えないルーマニアが、金メダル数で2位、メダル合計数で3位の結果を残したことである。当時、ルーマニアはニコラエ・チャウシェスク大統領の圧政の下、庶民はどん底の生活を強いられていた。それにもかかわらず、ルーマニアがオリンピックで素晴らしい成績を残したことは、逆に彼らの資源配分の偏りと、オリンピックを国威発揚の機会として利用しようとした政治の意図が見えて興味深い。チャウシェスク大統領は、5年後の革命時に処刑され、皮肉にも東西冷戦終結を示す代表的なアイコンとなった。
スポーツを和平に利用したケース

ここまで紹介した例は、スポーツをあまり好ましくないやり方で利用した例と言えよう。それとは逆に、スポーツのイベントを和平や国民のポジティブな一体感醸成のために活用した例もある。
その代表例が、南アフリカの初めての黒人大統領ネルソン・マンデラだ。マンデラは、20数年も牢獄に投獄されながら、それまでの支配層であった白人層との戦いを避け、話し合いによってアパルトヘイトを撤廃し、民主主義を実現した「赦し、話し合う」指導者である。その彼が苦労したのが、いかに国民の多数を占める黒人と、少数派の白人の融和を図るかということであった。そこで彼が活用したのが、1995年に南アフリカで開催される予定であったラグビーワールドカップである。
当時の南アフリカ国民のラグビーへの見方は以下のようなものが一般的であった。
「ラグビーは白人たちにとって、自らの存在感を示すことのできる誇りの源だった。彼らは、緑と黄色のユニフォームを着た大柄で力強い白人選手がいるスプリングボックスという南アフリカ代表チームを熱烈に応援していた。
"ヘルメットもかぶらず防御もしないまま、激しくぶつかり合う、スピードあふれるこのラグビーというスポーツほど、南アフリカの白人のアイデンティティを表すものはないだろう。そのため、黒人解放活動家は、ラグビーを白人の野蛮さのシンボルとみなし嫌悪してきた。そして、南アフリカの黒人は、スプリングボックスの試合相手を、文字通り『敵の敵は味方』として、応援するのが常だった。南アフリカ代表チームの負けが、まるで、自分たちの勝利につながっているかのような錯覚を抱いていたのだ」(『信念に生きる――ネルソン・マンデラの行動哲学』(リチャード・ステンゲル著、グロービス経営大学院訳、英治出版))"
こうした中、マンデラは、チームの主将であったフランソワ・ピナールとコミュニケーション深める。そして、説得してスプリングボックスに貧困地区を訪問してもらったりする。当初こそ軋轢はあったものの、黒人の間でもチームの人気は徐々に高まり、チーム内外で「南アフリカの代表」という意識が高まってく。そしてワールドカップでも勝ちあがり、最後はニュージーランド代表のオールブラックスとの決勝戦も制し、チャンピオンに輝くのである。
まるで映画のようなストーリーだが、実際にハリウッドがこの題材をほうっておくはずもなく、『インヴィクタス-負けざる者たち』(クリント・イーストウッド監督)として映画化されている。スポーツの持つ不思議な力を感じ取ることのできる作品である。ご興味のある方はぜひ鑑賞されたい。
スポーツが人種間の融和に働いたという意味では、1998年にフランスで開催されたサッカーのワールドカップも記憶に新しい。ヨーロッパの先進国は移民問題に悩むケースが多いが、ご多分にもれず、当時のフランスチームの主力も、ジネディーヌ・ジダンやマルセル・デサイーといった旧植民地圏出身のチームであった。当初は「これは真のフランス代表ではない」というフランス人らしいシニカルな批判もあったが、チームが勝ち進むにつれて、そうした声は小さくなり、チームはまさに人種融和の象徴となった。それは決勝のブラジル戦勝利で決定的となり、フランスは一時の人種融和の美酒を味わった(残念ながらそれは長続きしなかったのだが、それについては後述する)。
このように、スポーツ、特に、オリンピックやワールドカップといった大舞台でのスポーツは、その注目度ゆえ、うまく用いると、国民を一体化させる精神的柱ともなるし、逆に悪用すれば、国民を洗脳する武器ともなる。本来スポーツは政治的にはニュートラルであるのだろうが、ニュートラルであるからこそ、為政者の意図によって、良くも悪くも用いられ得ると言えよう。
ビジネスとナショナリズム
ここでビジネスとナショナリズムの関係を見ておこう。はたしてナショナリズムはビジネスにとって敵なのか味方なのか。
答えから言えば、「両方」ということになるだろう。プラスの側面から言えば、たとえば日本企業にとって、日本人が自国メーカーの製品やサービスを優先的に利用してくれることは、少なくとも短期的にはその企業にとって嬉しい話である。
一方、冒頭に見たように、偏狭な領土ナショナリズムで健全なビジネスでの交流が阻害されることはお互いにマイナスであることは言うまでもない。その他にもナショナリズムがビジネスにマイナスの影響を与えうる典型例としては、以下が考えられる。
・失業問題や不況と絡んだ外国人労働者や外国製品の排斥
・自国文化が侵食されることへの過度の反発
たとえば前者であれば、かつて日本製品が米国で打ち壊された映像をご記憶の方も多いであろう。最近では、日本企業を狙ったとしか思えないいくつかの訴訟の裏にもナショナリズムの匂いを感じ取ることができる。
本来友国であるはずのアメリカですら、時としてそうした動きが起こるという点は重要だ。そして、政治家の中には一定比率、それを利用し、自身の地位や発言力を高めようとする人間が存在するものである。ナショナリズムは人間の情動に訴えかけやすいし、愛国心を試す「踏み絵」としてそうした問題へのスタンスが問われることが多いという現実もある。それゆえ、少数の大きな声が拡大しやすい。したがって企業としては、最初は小さな問題と思っていたものが、雪だるま式に大きくなって自社に予想外の悪影響が起きないよう、慎重に社会や政治の動きをウォッチしなくてはならないし、火の粉が身に降りかかった際の危機対応能力を身につけることも必要である。
ちなみに今回、ユニクロを運営するファーストリテイリングは、先述の張り紙問題について、「(前略)弊社にて調査いたしましたところ、上海郊外の一店舗におきまして、9月15日午後、当該店舗の現地従業員が独自の判断により、上記内容の張り紙を掲示し、約40分後、撤去していた事実が判明いたしました。今後は、二度とこのような事が起こらないよう社内徹底してまいります」とのコメントを出した。筆者には比較的妥当な対応と思えるが、日本人の中にも、「この程度では生ぬるい」という声は少なくない。外国と自国の2種類のナショナリズムとどう付き合うかは、極めて高度なバランスを要する営みと言えよう。
かつてサミュエル・ハンチントンは、著書『文明の衝突』において、21世紀は、イデオロギーやナショナリズムの争いになると警鐘を鳴らした。ITの進化で情報があっという間に流れる昨今、イデオロギーやナショナリズムのうねりやその可能性について、企業も冷戦時代とは違う意味で、ナイーブではいられない時代に突入したのは間違いない。
スポーツはナショナリズムとどう付き合うべきか?
スポーツとビジネス。いずれもナショナリズムと無縁ではいられないが、その関わり方はここまで見た事例からもわかるように、やや異なっている。
ビジネスの場合は、グローバル経営の中でナショナリズムに絡んだ動きが自社のビジネスにどのような影響を与えるかという側面がまずは優先事項となろう。そして、場合によってはロビー活動などを通じて政府を動かし、ビジネスが正常に機能するように計らうことが眼目となる。
それに対して、スポーツの場合は、ナショナリズムの「道具」とされやすいという点に大きな違いがある。それはスポーツの持つ目立ちやすさや分かりやすさ(勝った、負けたなど)、高揚感のもう1つの側面でもある。しかも、企業に比べるとロビー活動などをする資金や人材は少ない。
こうした中でどのようにナショナリズムとのバランスを取っていけばいいのか。あまりにこれを否定しすぎると、金銭面や精神面でのサポートも得られないし、「国を代表して戦う」という自身のモチベーションも削ぐことになる。逆に、近寄りすぎると今度は好ましくないレッテルを貼られてしまいかねないし、グローバル化の進む昨今、自らの活動領域を狭めてしまいかねない。
スポーツにはもう1つの難しさもある。先に1998年のフランスサッカーチームの優勝が人種融合の象徴となったという話を書いたが、この先には後日談がある。2010年の南アフリカ大会(日本人にとっては、本田圭佑選手らの活躍が記憶に新しい)では、フランス代表チームはグループリーグで1勝もできず早々に姿を消してしまったのである。さまざまな理由が挙げられたが、次の記事がそれらをコンパクトに集約している。
"「(前略)『政治とスポーツが作り上げた人種融和の虚構まで崩れ去った』。こう指摘するのは、カーン大学のパトリック・バソール准教授(社会学)だ。
W杯優勝チームにはアラブ系、アフリカ系、中南米系の選手が多く、国民的英雄のジネディーヌ・ジダン選手もアルジェリア系だ。現在の代表チームの主流も非白人選手。移民国家フランスの社会の下層で多くの移民、その子孫が貧困にあえぐ中、その『夢』をつなぎ留めてきたのがサッカーだった。しかし、バソール氏は『(移民を含む一部選手による)買春や薬物使用、マフィアとの接触など多くの問題が表面に出てきた』と、『夢』の効果に限界が見え始めた、とみる。
『恥知らず』な一部選手に敗因を求める声も後を絶たない。評論家らは『愛国心を持たず、国歌も知らない』『大金を得られないW杯では手を抜き、フランスに所得税を納めないと吹聴する』『他人への敬意を持たない』と散々だ(以下略)」"(『YOMIURI ONLINE』2010年6月24日)
この例がすべてを物語っているわけではないが、スポーツの場合、「勝利」という果実が伴ってこないと、すべてが否定的に語られる傾向が強いという問題も実は大きい。ラグビーを国家融合の1つの手段として用いたマンデラ大統領のケースでも、優勝とは言わないまでも、ある程度の成績が残せなければ、あれほどの効果はもたらせなかった可能性は高い。
とは言えスポーツ、特に国際スポーツにおいて勝利することは難しいことだ。サッカーで言えば厳しい欧州予選をかいくぐるだけでも難しいことなのに、本大会の予選リーグで負けたらそれまでの歴史が全否定されてしまうというのは、選手にとっては辛いことだ。ある意味、ビジネスで利益を上げること以上に難しいことと言えよう。
こうした中で、スポーツはナショナリズムとどう対峙すべきなのか。筆者も現段階で明確な解を持ち合わせているわけではないが、ポイントを挙げるとすると、「自分が道具として利用されているのではないか」という健全な批判精神を持つことと、特に有名選手ほど自分自身の発言や振る舞いの影響力の大きさを知ることであろう。
いずれも自身を冷静かつメタに見る必要があることは言うまでもない。同時に高度なバランス感覚も要求される。これらを満たすことは決して容易ではないが、中にはその振る舞いや言動が参考になる選手も多いはずだ。
我々ビジネスパーソンとしては、そうした彼らの振る舞いの中にヒントを見出したいところである。スポーツにせよビジネスにせよ、本来は人間の幸福や精神的充足感に寄与するもののはずだ。何か好ましくない圧力が働き、その本来のあり方が脅かされるリスクには敏感でありたいものである。